トリコロールと日の丸 「親日」フランスの謎を解く(単行本)

日仏はともに「宗教帰属」で無関心がデフォルト! プロテスタントの国にはない「食事を味わう」文化も日仏共有!
日本とフランスは160年に渡る交流の間、互いにリスペクトと憧れを抱き続けてきたという他国にはない特別な歴史があります。本書は、半世紀近く日本とフランスのふたつの国を生きてきた著者が、文化や美学への深い共感によりつちかわれた日本とフランスの相愛関係の秘密と、西洋世界における日本の立ち位置を分析し、これまでほとんど指摘されたことがない、あたらしい日仏比較文化論を語ります。
カバー画・本文イラスト=じゃんぽ〜る西。
著者のコメント
2022年春にカナダのケベックを旅した時に突然日本とフランスのパラドクシカルな相似に気づいて、書き始めたものです。2023年11月に恵比寿の日仏会館でこのテーマでトークをして、その後、私の音楽活動と日本との関係について加筆してようやく出版が決りました。
昨年10月の同じ日仏会館でのコンサートにご家族で来てくださったじゃんぽ~る西さんがイラストを描いてくださいました。
コンサートの世話をしてくれた丸山有美さんは白水社『ふらんす』の元編集長で、私も西さんも同じ頃に連載していたので、彼のマンガも知っていました。
編集者によると西さんの読者は女性が多く私の読者は中高年男性が多いそうで(どうやってそんなことが分かるのでしょう)、西さんの参加で新しい読者層を期待しているそうです。
私の本はいわゆる「在仏日本人によるフランス生活」のエッセイではないので少し心配ですが、今まで書きたいと思ってまとまっていなかったことを広げることができたので一息つけました。
2003年から2024年まで5回に渡る日本公演に協力してくださった方々への感謝も込めることができたのも嬉しいです。
お手に取って読んでいただければ幸いです。
出版社: 秀和システム
竹下 節子 著
じゃんぽ〜る西 画
ジャンル 人文
書店発売日 2025/03/08
判型・ページ数 4-6・248ページ
定価 1980円(本体1800円+税10%)
ISBN 9784798074412
オカルト2.0

西洋エゾテリスム史と霊性の民主化
秘教の系譜が照らし出す、現代の不安と希望
中沢新一氏推薦「この国で長いことタブー語のような扱いを受けていたオカルトという言葉に本格的な解明の光を当て、文化としての正当な位置付けを回復しようとした勇気ある書物!」
メスメルとパラケルスス、エリファス・レヴィとルネ・ゲノンとユリウス・エヴォラ、「ヘルメス文書」とキリスト教、神智学とエニアグラム、エサレン研究所とシュタイナー……。
パリ在住の文明史家がエゾテリスムの歴史をたどり、欧米のオカルティズム最新事情を考察を交えて、レポートする。
著者のコメント
目には見えない世界、五感でキャッチできない世界、AIにも検索されない世界、そういう世界がどんどん侵食されています。
音楽も、デジタル処理されたりプログラミングされたりしているものは、「ノイズ」のない世界です。
生の音楽演奏や踊りや語りの実践や鑑賞を通して受け取る無限のノイズこそは、より大きな「全体」を生きることを教えてくれるものです。
「祈り」や「瞑想」を通してそのディメンションに到達する人もいますが、それをコーチングしてビジネスにする人もまた出てきます。
オカルト、エゾテリスムの伝統は、あらゆる正統宗教と魔術や負の情動との尾根をずっとたどってきました。
2020年に人々を孤立させたコロナ禍は、オカルトに、宗教を介さない「救い」の脇道のひとつを開きました。
2020年から数年にわたるコロナ禍「対策」によって、民主主義国か全体主義国かを問わず、あらゆるタイプの「政府」が、人々を恐怖で統治し、情報を操作し、人々の識別知を封印できることが明らかになりました。
今こそ、全ての人が自由に真実の探求に向かうことが可能な新しい時代を目指すべきではないかという思いを語ったのがこの本です。
カオスの中で漂う人が増えている時代に
キリスト教文化圏は、彼らにとっての異文化であるアジア、アフリカへの進出や「新世界」の発見を通して未知の伝統や世界観を「発見」することになった。その過程で、エゾテリスムやオカルトは他文化・他文明の宇宙観を柔軟に吸収・混淆し、自らを豊かにすると共に、「人類共通」のスピリチュアリティを意識する普遍主義へと向かった。
表世界の既成システムである宗教・科学・政治の「権威」が自分たちの優越性・真実性を振りかざして異文化を「征服」していった功利主義や覇権主義とはまったく別の流れがあったわけだ。
その意味では、エゾテリスムやオカルトは、「多様性」を包含するグローバルな潮流を常に維持してきたといえるだろう。その一方、キリスト教文化圏における宗教・科学・政治の方は、「自分たちの普遍性」を帝国主義的に広げた。
そこに産業革命による生産力の著しい増大とそれに伴う経済活動の拡大が加わって世界の「西洋化」が加速する。特に、カトリック的な価値観、つまり霊的な努力によって救われるという「伝統」と決別したプロテスタント文化圏では、生産性の拡大と富の蓄積自体が偶像的な指標となっていき、他の地域を席巻した。
その過程で、共産主義イデオロギーによる別の形の絶対主義(労働者が支配することで理想世界が出現するが、その過程では党独裁が必要とする主義)も登場したが、二〇世紀末に「冷戦」が終わってからは、政治的なカオスが始まる。「成長」を基準にする経済指標だけが「主流」となって、その影では、宗教も科学も政治もカオス化してしまったのだ。言い換えると、宗教も科学も政治も「経済」と結びつくことで、経済至上主義となり、それまで「優越性」を体現していたはずのシステムが崩壊していったのだ。
裏打ちすべき表側のコスモスが崩壊したことで、エゾテリズムやオカルトと宗教、科学、政治の境界が曖昧になった。
「先進国」といわれていた地域でも「科学」を名乗る新宗教、疑似科学、代替医療が跋扈している。見渡せば、宗教原理主義を打ち出す政治体制が次々と登場し、民主主義の看板を上げ続けながら実態は一部の富裕層の利益を優先する国、宗教をナショナリズムに利用したり、核兵器を伴う軍事力や経済力で新たな実質的な植民地政策を展開したりする国もある。
そのカオスの中での閉塞感や生きづらさが、オカルトやエゾテリズムのマーケットを増大させることになった。デジタル・ツールの進歩で情報収集の選択肢が増えたわけではない。むしろ、端末の前で分断しながら特定の思想への帰属感を増大させるマインドコントロールというリスクが高まっているのが実情だ。
カオスと多様性は似て非なるものなのに、今は「多様性」の名のもとに、カオスの中で孤絶して漂う人が増えている。そんな時代に、長い間、恣意的で支配的な体制としての「コスモス」の裏側で「多様性」を柔軟に担保してきたオカルト世界の知恵を有意に復活させる道はあるだろうか。
実存的な不安や恐怖から「自由」になることを目指す
オカルト2・0は、人類がいつの時代のどこの文化でも、個人の心身を超えたスピリチュアリティを求めてきた長い歴史の膨大な蓄積に「自分の部屋」からアクセスが可能になった時代に、生まれる。
これまで見てきたように、「実践」にまつわるサービスの提供や方法論の提供の中には、明らかにビジネスだとわかるものがある。マーケティングの手法として、まず終末論的な言説で不安を誘い、怖がらせたり絶望させたりするものはわかりやすい。それらに取り込まれないためには、個人の生死に関わるような運命は誰にも見通せないし、変えることもできないことをまず認める必要がある。
スピリチュアリティとは「個別」のものではなく、個人の心身にも、大自然の営みにも、宇宙の動きにも内包されていながら、それを超えたところにある。真のスピリチュアリティへのアクセスとは「分かち合い」を前提としている。「私」の得たものを分ち合うというのではなく、「すべてをそのまま分かち合う」ことでしか触れることができない何かのようだ。
それは「多様性」のもとに、閉塞したり、逆に競合したり、権力関係を生むようなものではない。どんなに多様なものでも、時と空間を超えてさえ、つながっている。
オカルト2・0 は「隠れたやり方」で何かを実現したり、他人に影響を与えたりするためのものではなく、まず、一人ひとりが実存的な不安や恐怖から「自由」になることを目指すきっかけとして活用できる。本当の「自由」というのは何も制限がなく好き放題にできるという状態ではなく、原初の不安や恐怖を克服して得られるものだ。
そして本当の自由は、他者の不在の中や他者を無視したり他者に優越したり他者を管理したりすることで発揮できるものではない。同じように自由な他者とのつながりの中で現れる。
初期キリスト教会でパウロは、そのことをすべての人が霊(スピリット)によってキリストの「体」を構成していると形容した。その箇所を引用してみよう(コリントの信徒への手紙一 12,7-27)
〈一人一人に霊の働きが現れるのは、全体の益となるためです。
ある人には、霊によって知恵の言葉、ある人には同じ霊に応じて知識の言葉が与えられ、ある人には同じ霊によって信仰、ある人にはこの唯一の霊によって癒やしの賜物、ある人には奇跡を行う力、ある人には預言する力、ある人には霊を見分ける力、ある人には種々の異言を語る力、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。
しかし、これらすべてのことは、同じ一つの霊の働きであって、霊は望むままに、それを一人一人に分け与えてくださるのです。
体は一つでも、多くの部分から成り、体のすべての部分は多くても、体は一つであるように、キリストの場合も同様です。
なぜなら、私たちはみな、ユダヤ人もギリシア人も、奴隷も自由人も、一つの霊によって一つの体となるために洗礼(バプテスマ)を受け、みな一つの霊を飲ませてもらったからです。
実際、体は一つの部分ではなく、多くの部分から成っています。
足が、「私は手ではないから、体の一部ではない」と言ったところで、体の一部でなくなるでしょうか。耳が、「私は目ではないから、体の一部ではない」と言ったところで、体の一部でなくなるでしょうか。
もし体全体が目だったら、どこで聞きますか。もし全体が耳だったら、どこで嗅ぎますか。そこで神は、御心のままに、体に一つ一つの部分を置かれたのです。すべてが一つの部分であったら、体はどこにあるのでしょう。しかし実際は、多くの部分があっても、体は一つなのです。
目が手に向かって「お前は要らない」とは言えず、また、頭が足に向かって「お前たちは要らない」とも言えません。
それどころか、体の中で他よりも弱く見える部分が、かえって必要なのです。私たちは、体の中でつまらないと思える部分にかえって尊さを見いだします。実は、格好の悪い部分が、かえって格好のよい姿をしているのです。しかし、格好のよい部分はそうする必要はありません。神は劣って部分をかえって尊いものとし、体を一つにまとめ上げてくださいました。
それは、体の中に分裂が起こらず、各部分が互いに配慮し合うためです。一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。あなたがたはキリストの体であり、一人一人はその部分です〉
実際に、すべての細胞は多様な臓器を作っているし、有機的な動的平衡の状態にある。量子レベルでは不思議な動きをしているし体が死んでも消滅することはない。
仏教的な表現では、大乗仏教の『涅槃経』にある「一切衆生【いっさいしゅじょう】悉有仏性【しつうぶっしょう】(一切衆生 悉【ことごと】く仏性有り)」という有名な言葉が想起されるかもしれない。
禅の言葉には「遍界不曾蔵(遍界、曾【かつ】て蔵【かく】さず)」というものがある。「全宇宙には何物をも包み隠すことはない。真実はいたるところにありのままの姿で堂々と顕現している。一切万象がそのまま本来の面目の現れである」という意味だ。すなわち、「神秘」や「霊」は、オカルトのように隠れていたリ隠されていたりするわけではない。超自然とは「見えていない(あるいは見ようとしていない)自然」であるだけで、仏教的にはいわゆる「超越」も存在しない。
普遍宗教の教えは、「私たちには本来、すべてが与えられている。そして私たちはすべてとつながっている」と示唆する。顕教も密教も、エゾテリスムもオカルトも、占星術も天文学も、マクロの世界もミクロの世界も、科学も哲学も、生も死も、病も癒しも、争いも慈悲も、すべてを与えてくれる「真実」の方向にひと押しされさえすれば、その先に見えてくるのは、ニーチェの語った「大いなる健康」なのかもしれない(詳しくは『喜ばしき知恵』一八八二年を参照)。
創元社 200頁 定価 2,420円(税込)
刊行日: 2024/4/25
ISBN: 978-4-422-70177-6
判型:四六判 188mm × 128mm
造本:並製
キリスト教入門

キリスト教抜きに世界のスタンダードは理解できない!
旧約・新約聖書を丁寧に解説、「救世主」「アダムとイヴ」「三位一体」「クリスマスツリーと十字架」「原理主義」「進歩主義とグローバリゼーション」などのキーワード/トピックから、キリスト教理解を立体的に組み上げる。信仰生活のリアル、各宗派とのかかわり方など、実践的なガイドも盛り込んだ、非キリスト教文化圏に住まう「普通の日本人」のための最良の入門書! 混迷の時代、普遍宗教が示す未来とは?
著者のコメント
選書メチエの知の教科書シリーズ『キリスト教』の文庫化です。
実はこの本をメチエから出した時よりも、世界の状況ははるかに悪くなり、キリスト教の基本を知ることの意味はさらに深くなったと思います。宗旨に関わらず、宗教音痴、無関心は、リスク大です。愛と平和を唱えたことで既成の宗教権力や政治権力によってあっさり殺されてしまったイエスから始まり、今や非難の的にもなっている「西洋」のベースになった宗教の本質を探るツールとしてどうぞ。
講談社学術文庫
288頁 定価 1221円(本体1,110円)
刊行日: 2023/7/13
ISBN: 978-4-06-532554-4
コンスピリチュアリティ入門

スピリチュアルな人は陰謀論を信じやすいか
横山 茂雄 著 / 竹下 節子 著 / 清 義明 著 / 堀江 宗正 著 / 栗田 英彦 著 / 辻 隆太朗 著 / 雨宮 純 著
著者のコメント
創元社から発売の共著です。
コンスピリチュアリティというのは「陰謀論」と「スピリチュアル」が合体したというか、互いに親和性をもって進化してきた現象のことだそうです。
私はそれをフランスからの視点で書いてみました。
この本の全部について読んで分析したわけではありませんが、着眼点を見て、いろいろ考えさせられました。
この状況は、クライシスでもあり、実は、ポスト・ポストモダンの混迷の中から新しい知のパラディグムを模索するきっかけになるように思われてきました。
ウォーキズムから、反知性主義から、プーチンのスピリチュアリティまで、すべてが、何から生まれてきてどこへ行こうとしているのかが見えてきたようにも思えます。一見、荒唐無稽で非科学的な言説が、アングロサクソンの共同体主義の中で、ポスト・プロテスタンティズム、ポスト・ビューリタニズムの流れを作っているのです。フレンチセオリーとされているポストモダンの脱構築とは似て非なるものです。
「西洋近代」が掲げた最もましなイデオロギーであるユニヴァーサリズムがつぶされようとしています。
日本人は「白人」ではないという強みがあります。
カナダのある演劇が、アジア人と黒人を排除したそうです。
ジェンダー、性別などないことにして取っ払え、といっているのに、男は女になれるし女は男になれる、異性愛や同性愛も存在するのも矛盾ですが、肌の色はないことにはされません。レイシズム批判は「赦しのない批判」です。
アメリカの「白人」は「黒人」に謝罪することだけが許されていて、「黒人」になることは黒いメイクをすることすら許されていません。ジェンダーは自己申告できるのに人種は自分で変えられない。
私は人種別統計を禁じるユニヴァーサリズムの国フランスに住んでいて、今や「反差別主義者」から吊るしあげられる「白人」でもなく、「男」でもなく、「若者」でもないという立ち位置で見えてきたり論じたりすることがたくさんあってラッキーです。
ここまで書いたこと、意味が分からないかもしれませんが、このコンスピリチュアリティというのは「カルトとオカルト」との関係にも似ています。
カルト宗教は宗教の逸脱ですが、オカルトは宗教の根に関わっていて、実は最も人間的な部分に訴えてくるものでもあります。
オカルトについて比較宗教的にもアプローチする本を創元社から出版予定で今執筆中です。その中でプーチンのスピリチュアリティにも触れます。プーチンと言えば、正教を利用しているだけで、スピリチュアルな言説など口実に過ぎない、と西洋からは思われていますが、ソ連崩壊のリアクションにはパガニズムが跋扈したし、ロシア正教だけではなく、広いロシアのステップ地方のコスミックなシャーマニズム、イスラムスーフィズムの影響も受けています。ソ連時代にも、潜水艦の位置を見つけるのに「霊能力者」を起用していたという話もあります。三つの一神教をまとめ上げたフランスのルネ・ゲノンのオカルト本はロシア語に訳されて流布していました。
社会現象としてのコンスピリチュアリティをアングロサクソンの外から見ながら、今の世界の混迷の中で、どの方向に一番ヒューマンな解決策を見出せるかと模索中です。
とりあえず、この『コンスピリチュアリティ入門』への参加に声をかけてくださった関係者に感謝します。
内容紹介
コンスピリチュアリティに関する初の論考集
「Qアノン」、新型コロナ生物兵器説、自然食、イルミナティ、そして爬虫類系宇宙人による人類の支配。
政治的影響力を持つまでに至った陰謀論と、その背景にあるとされるスピリチュアルな世界観。
この2つをともに論じることを可能にする注目の視座「コンスピリチュアリティ」を日本で初めて紹介した論集。
気鋭のライターから西洋オカルティズム研究の大家まで、多彩な執筆陣が明らかにする陰謀論+スピリチュアリズムの最前線。
創元社
叢書パルマコン・ミクロス03
296頁 定価:2,420円(税込)
判型:四六判 188mm × 128mm
造本:並製
刊行日: 2023/03/23
ISBN:978-4-422-70127-1
疫病の精神史 - ユダヤ・キリスト教の穢れと救い

キリストは手を洗わなかったーーー近代の衛生観念を先取りしたユダヤ教に対しキリスト教は病者に寄り添い「救い」を説く 古代から現代まで、人類と病の歩みを問いなおす――。
ペスト、赤痢、コレラ、スペイン風邪、新型コロナ――、古代から現代まで、人類は疫病とどのように向き合ってきたのか。律法により衛生管理を徹底し「穢れ」を排除したユダヤ教と、病者に寄り添い「魂の救い」の必要性を説いたキリスト教。二つの価値観が対立しつつ融合し、やがて西欧近代という大きな流れへと発展してゆく。聖書に描かれた病者たち、中世の聖者や王が施す治療、神なき現代社会で「健康」を消費する現代医学。疫病に翻弄される世界の歴史を描き、精神の変遷を追う。
目次より
はじめに――いま、宗教の役割とは何か
序 章 新型コロナとキリスト教
第1章 疫病は聖書でどう描かれたか
第2章 キリスト教と医療の伝統
第3章 疫病と戦う聖人たち
第4章 イエスは手を洗ったのか――「清め」と衛生観念
第5章 疫病に翻弄された西洋――ペスト・赤痢・コレラ・スペイン風邪
終 章 近代医学か宗教か
おわりに――思考停止に陥らないために
著者のコメント
 2021年4月30日、ベネズエラで「貧者の医師」として慕われたホセ・グレゴリオ・エルナンデスJosé Gregorio Hernándezがローマ教会から福者の列に加えられた。
2021年4月30日、ベネズエラで「貧者の医師」として慕われたホセ・グレゴリオ・エルナンデスJosé Gregorio Hernándezがローマ教会から福者の列に加えられた。
エルナンデス医師は、聖職、修道者を志した敬虔なカトリックでフランシスコ会第三会(世俗会)のメンバーである。ベルリンやパリでも学び、ベネズエラに顕微鏡を導入し、先端医学の枠組みを作った。
第一線の医師であるにもかかわらず、常に貧しい人々に寄り添い、スペイン風邪が猛威をふるった時も巷の病者のために徹底的に尽くした。1919年6月、カラカスで、いつも往診していた貧しい女性のために薬を購入する薬局の前で車にはねられて病院に運ばれた。終油の秘跡を受けた後、「ああ。聖母様」とつぶやいで死んだという。何千人もの人が葬儀に参列し、カラカス
のカテドラルに埋葬された。
人々からは生前からすでに「聖人」だと呼ばれていた。
彼が亡くなった後、治癒を祈る多くの人が奇跡的に癒されたという。
すでに、民衆宗教であるサンテリアの神のような扱いを受けるようになっていた。
で、カトリック教会が正式な「聖人」とするために、まず福者とする調査を始めた。
そのためには医学的な検証を経た「奇跡」が必要で、2017年3月に強盗による襲撃のあおりで頭に弾丸を浴びた少女の例が調査された。大手術で命は助かったものの、頭頂部頭蓋骨の一部を切除、意識を取り戻しても深刻な神経障害で後遺症が残ると医師たちは宣告した。少女の母はエルナンデスに祈り、数日後、少女は何の後遺症もあらわすことなく退院した。医学的には説明できなかった。この「奇跡」が、2020年6月19日にローマ教皇から認定され、エルナンデスは今年晴れて福者となったわけだ。
キューバ由来のサンテリアなど、中南米には黒人奴隷がアフリカから伝えた民俗宗教とカトリックの混淆した宗教がいろいろある。
それについて、一時は、奴隷たちが、カトリック教会を欺くために、各種の聖人を崇敬していると見せかけて実はそれぞれに多神教のさまざまな神を託して祈ってきたのだという説があった。
実は、その反対で、Kali Argyriadisの「ハバナの宗教」の中の引用によると、カトリック教会が、それぞれの神に対応する聖人をあてがったのだそうだ。1687/9/16の教皇シノドで、アフリカの宗教の民間信仰に対してカトリックの信心行為を当てはめるようにと司祭たちに指示があったという。1792年にもアフリカ人に、彼らの神々の代わりに、それに対応するカトリックの聖人を崇敬するようにという政策「Bando de buen gobierno y policía」が施行されている
。
カトリックの植民者には黒人奴隷への宣教、キリスト教化を望まない者もいた。彼らのために教会を建てたり、主日である日曜を休息の日としなくてはならないなどコストがかかるからだ
。
サンテリアというのは聖人santosを揶揄したものだ。カトリック教会の「聖人崇敬」というのは偶像崇拝としてプロテスタントからもイスラムからも「多神教」だと批判されるのだけれど、「神の愛」の証し人をいわば表彰し続けて得られる
信頼感や安心感などを思うと、十分なメリットがあったと思われる。
人々はエルナンデス医師に「聖人」を見たが、エルナンデス医師は、全ての貧しい人、全ての病める人の中に「イエス」を見ていた。それはイエスのメッセージでもあり、十字架上で殺されたイエスを復活のキリスト(救世主)として出発したキリスト教の根幹にある。
日本で「貧者の医師」というと「赤ひげ」を思い出す。日本医師会は2012年から「赤ひげ大賞
」というのをオーガナイズしているが、「地域の人と結びついた地域医療の貢献者」というのがコンセプトのようで、「赤ひげ」のモデルとなった貧者救済の小石川養生所とはタイプが違う。
日本にも医師で僧侶という方がいるが、仏教と医療の関係と、キリスト教と医療の関係は根本的に違う。もちろんどちらがいいとか悪いとかの問題ではないし、患者との関係では医師ひとりひとりの人格が決定的になる。
けれども、長い間戦争がなく医療が発達した「先進国」ではどこでも、ビジネスとしての医療が定着し、消費者としての患者もだんだんとそれに慣らされていった。
そんな時代に「世界を襲うパンデミック」と喧伝されて登場したのが新型コロナウィルス感染症だ。
遠い中国の出来事だと思っていたのが、あっという間に、イタリア、スペイン、フランスというカトリック国に広まった。しかも、キリスト教の典礼が目白押しの復活祭のシーズンだった
。
このコロナ禍に対応する政府、社会のリアクションが、ヨーロッパの国々のそれぞれのメンタリティの差を明らかにしたのは興味深かった。政治、経済、社会の反応と、宗教の反応はまた別だった。
1年の間、それをじっくり観察することができた。まさにコロナ・フィールドワークといったところだ。
その中であらためて確認できたのは、キリスト教文化圏が医療と貧困に対して持ち続けてきた視線がどのようものだったのかということだ。
そんなタイミングで、エルナンデス医師が列福されたのを見て、あらためて、生と死、医療と健康と「霊性」との関係が、「人生」の意味に深くかかわっていることを知らされた思いだ。「神」という作業仮説が、実存的な危機においてどのように必要不可欠になるのかも実感した
。
『疫病の精神史』に出てくる、疫病の中で人々に尽くし病を得た聖人たちを見ているとそれが想像できる。
多くの人が病み、多くの人が苦しみ、多くの人が死んでいった。疫病が終息してもしなくても
、人はやがて他の人と別れる時が来る。けれども、決して途絶えることのない「つながり」も
また存在する。そんなことを感じながらこの本を分かち合うことができるなら、それに勝る喜
びはない。
ちくま新書 新書判 240頁 定価 本体820円+税
刊行日: 2021/6/10
ISBN: 978-4-480-07406-5
JANコード: 9784480074065
カトリック・サプリ5 新しい未来を生きるあなたへの25のメッセージ

2021年2月10日発売
演会、演奏会等発信の機会が閉ざされたコロナ禍で、日本に行かれない今だから、ぜひ伝えたいことがあるという著者。
月刊誌「カトリック生活」の好評連載“カトリック・サプリ”に2017〜2020年に掲載された中から厳選し、加筆・再構成された17編に加え、「今、あなたに届けたい!」という著者の熱い思いが込められた書き下ろし8編を含む25編は、未来を絶望することなく、与えられた冒険にチャレンジしようと呼びかける。
目次
その1 試練のときこそ優しくなろう
エディット・シュタインとエティ・ヒレスム
ノートルダムが教えてくれたこと
感染症の「時」の気づき
感染症とサマリア人
愛の神への祈り方
その2 “みんな”の中に悪魔が隠れていることもある
マグダラのマリアがつなぐもの
罪悪感を消す
コロナ禍と「自由」
道徳と平和
福音の真珠
その3 困っている隣人に手を差し伸べるのは難しいことですか?
フランスと聖ヨセフ
カトリックでよかった
いのちが「歩み」である話
聖霊の舞うとき
本当の「全人医療」
その4 神の恵みはどんなときにもあふれている
ジャンヌ・ダルクに学ぶ三つのこと
コロナ禍の自粛と神の要請
慎重であること
時とはいのちのことだ
教会の危機ってなんだろう
その5 戻る場所を探すのではなく新しい未来を!
イエスを翻意させようとする母
「コロナ危機」の復活祭が教えてくれたこと
「私」の向こう側
「神のみ旨」を考える三つの話
いのちを愛する生き方
著者のコメント
去年の今ごろ、「神のトリセツ」というテーマでいろいろ書き始めていた。
「神頼み」について考えるところがあったからだ。
人は事故や災害や試練に遭ったり病気になったり、挫折したりするたびに、神仏に祈り、それがかなえられないと、「どうして今? 」「どうして私だけが?」などと不当感に囚われて、「もし神仏がいるならこんな不幸や悪が放置されるわけがない」などと「信心」を捨てたり、敵意さえ抱いたりすることがある。「神」と人との関係は疑いや愛憎の繰り返しだった。
そんな時、コロナ禍があっという間に世界に広がった。
当然、多くの人は、「疫病退散」「病気平癒」「健康長寿」を祈るような気分になっただろうし、実際、数々のお守りが出回り、加持祈祷も繰り広げられた。一方で、宗教の集会がクラスターとなったり、イタリアで多くの聖職者がパンデミックの犠牲者になったり、神や宗教の「無力」を痛感した人や神の加護を信じられなくなった人もいただろう。
「神のトリセツ」は、コロナ禍の世界で、どのように希望をつないでいけるのかという問いに変わった。
同じような問いを発している人にこの本が少しでもヒントになればと願うばかりだ。
著者ブログでの紹介記事
ドン・ボスコ社 新書判 並製 232頁 本体740円+税
ISBN978-4-88626-674-3 C0216
女のキリスト教史 - 「もう一つのフェミニズム」の系譜
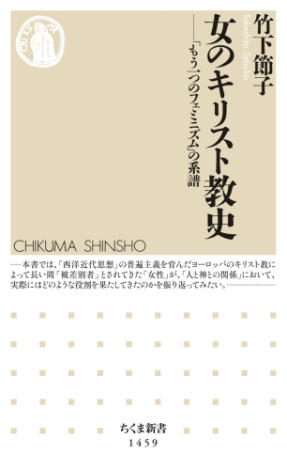
キリスト教は女性をどのように眼差してきたのか。聖母マリア、ジャンヌ・ダルク、マザー・テレサ…、世界を動かした女性たちの差別と崇敬の歴史を読み解く。
目次より
序章 フレンチ・フェミニズム――ジャンヌ・ダルクからカトリーヌ・ドヌーヴまで
第一章 イヴの登場――すべてはエデンの園から始まった
第二章 イエスの登場――イエスを育てた女たち
第三章 聖母の登場――マリア崇敬が女神信仰を温存した
第四章 聖女の登場――マグダラのマリアからマザー・テレサまで
第五章 魔女の登場――聖女になれない女たち
第六章 女性リーダーの登場――女子修道院と神の国
終章 神はフェミニストなのか?
著者のコメント
この本のもとになったのは、もう長い間温めていたフレンチ・フェミニズム本のプランと「#MeToo」運動の広がりだ。
もともと、アングロサクソンの犠牲者フェミニズムやジェンダーレス、同権論などと、フランスのユニヴァーサリズムに基づく平等主義とは全く方向が違う。そのフランスにさえ、冷戦後にはしっかりとアングロサクソン型新自由主義と同時に、共同体ロビー型フェミニズムがはびこってきた。
数年前、『「オバサン」はなぜ嫌われるか (集英社新書)』を書かれた社会学者の田中ひかるさんとお近づきになれた。で、フレンチ・フェミニズムを紹介するために「フランスにはなぜオバサンがいないのか」というテーマで、田中さんと往復メールをはじめ、発表したかったのだけれど、どの出版社からも、日本では「フェミニズム」本は難しい、と言われてしまった。けれども、アメリカ発の「#MeToo」運動が知られるようになったので、今こそフレンチ・フェミニズムについての本を出せるかも、と思ったのだ。
これまでも、アングロサクソンの共同体主義に対してフランスのユニヴァーサリズムを擁護する本を書いてきた。私が擁護すべきなのはユニヴァーサリズムだと最初にはっきり意識したのは、2003年初頭に米英軍がイラクに侵攻する前のいろいろなやり取りを通してだった。
それに合わせて、私にとってのユニヴァーサリズム擁護三部作である「バロック音楽はなぜ癒すのか」「聖女の条件」「アメリカにNOと言える国」を出すことになった。守備範囲としているバロック音楽からカトリック文化、猫好きに至るまで、私が学んできたユニヴァーサリズムの流れにあることをはっきり意識したからだ。
で、アングロサクソン型のフェミニズムとフランス型フェミニズムの違いも、実は、プロテスタント型メンタリティとカトリック型メンタリティの違いから発している。
いや、「カトリック型」といっても、ローマ帝国父権主義メンタリティと「イエス・キリスト」型メンタリティは全く違う。そして、プロテスタント型メンタリティといっても、ローマ帝国父権主義メンタリティのヴァリエーションのようなものだ。そこのところをはっきりさせるために、『女のキリスト教史』を書いた。
「女と神とキリスト教」というのが私のイメージだった。その「女」というのは共同体主義の中で社会的マイノリティの一グループとして扱われる意味での「女」ではない。この本でそのことが少しでも伝わることを祈っている。
2019年11月に訪日したローマ教皇フランシスコは、その超「父権的」な構造で「パパ」さまという仰がれ方をされているのにかかわらず、イエス・キリスト的なユニヴァーサリズムは徹底的に相対的弱者の側に立つということを明確にしている。イエスの養父であるヨセフは徹底的に聖母子に仕えた。「聖父」フランシスコの敬愛する聖人の筆頭が「聖ヨセフ」だ。フランシスコ教皇の発する本音が権力のある男たちに嫌われるのも、無理はない。
ちくま新書 新書判 272頁 定価 本体860円+税
刊行 12/05
ISBN 9784480072733
JANコード 9784480072733
超死生観

「死後」を豊かに生きるヒント!
満足・充実の現役生活は第1の人生、リタイア後が第2の人生。じゃあ、『今わの際』のその先にある第3の人生を、あなたはいったい、どう生きるおつもり?!さあ、さあ、さあ、さあ!
●主な目次
第1章 キリスト教文化圏と「あの世」(「死」の先にある「生」を楽しむ)
第2章 地域文化別・ヨーロッパ人の「生命観」(二つの「次元」、二つの「いのち」)
第3章 「死後の世界」との付き合い方(死後の世界を観測してみる)
第4章 「良き死」をどう生きるか(「良き死」の伝統とマニュアル)
第5章 スターティング・ノート作りの勧め(大きな人生と小さな人生;スターティング・ノートの作り方
著者のコメント
私のブログを編集した『渡り鳥の見たキリスト教』を今年初めに出してくださったフリープレスさんが出してくださった本だ。
今でも電子書籍で読める『ヨーロッパの死者の書』(筑摩書房)という本があり、ずっと愛読してくれている方もいるのだけれど、その系列の「発展形」だ。
私は疑い深いわりに「超常現象」好きで、宗教における「奇蹟」譚にもこれまで何度も触れてきた。そもそも「信じられない」ことを「信じる」とどうなるか、というプロセス自体に興味がある。まあ邪心があり過ぎるので、自分自身はそういう「超自然系奇蹟」とは縁が遠い。と言っても、年をとるにつれて、自分がこの時代に生まれてこういう生き方をして来ることができて、限りない大切な出会いをしてきたこと自体の「奇蹟」を身に染みて感じるようにもなっている。
この『超死生観』は、私の両親との別れを通して、だんだんと確信を持つに至った死生観で、このことをかなり前に偶然知り合った仏教関係の方にお話ししたところ、「スターティング・ノート」にとても興味をもっていただいた。その関係で、インタビューも受けたし、講演もさせていただき、日本のいろいろな宗教者ともご縁ができた。忘れられないのは、そのご縁で実現した2014年の築地本願寺での私のバロック音楽トリオのコンサートだ。そのコンサートの前に宗教社会学者の大村英昭先生(その翌年に亡くなられた)が「講和」の中で、私の『キリスト教の真実』という当時の新刊を絶賛してくださったのに驚いた(何しろ「真宗カトリシズム」という言葉を使ったことで大谷派から批判されたくらいにユニヴァーサルな視点を持っている方だった)。
で、この「超死生観」にあるスターティング・ノートの勧めというのも、特定の宗教とは関係がない。いや、無宗教でも無神論者でもOKの考え方だ。この世を離れる時に、一人でも、愛している人や、自分のことを愛してくれる人がいる場合に勧めたい。この世を去るという、まさに「この期に及んで」のタイミングに、もはやイデオロギーや宗派論などは関係がない、「愛の関係」を残し、養いたい、というだけだ。
近頃は、なにかというと、百歳長寿のハウツーものや、老後や相続で困らない方法、損しない方法、葬儀や墓の手配の「終活」、エンディングものの情報ばかりが広がる世界で、それとは別の見方を提供したかった。
想定読者が「今は一応元気な高齢者」なので、若い人はもちろん、「死ぬのは怖くない、今生き延びるだけで精いっぱい」などという方には向いていない。
でも、ある意味で「死ぬのが怖い」と思えるのは「余裕」のある人だと思う。その「余裕」を「恐れ」ではなく、「実は、まだ、与えることができる」という気づきへと向けてほしい、というのがこの本を書いた理由だ。
「不思議な話」もいろいろなエピソードもたくさんあるので、軽く読めると思うので、ぜひどうぞ。
四六判 並製 180頁 定価 本体1500円+税
発行:フリープレス
ISBN:978-4-434-26800-7
ローマ法王
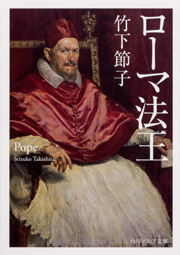
国際政治・外交・平和のキーパーソンであるローマ法王。
その歴史と現在。
著者のコメント
この本の出版経緯については「あとがき」にこう書いている。(抜粋)
二〇世紀末にこの本をちくま新書から出した時は、世紀末の終末論的な言説が横行していた。二度の世界大戦をくぐり抜けた後の冷戦時代には核戦争による人類絶滅の恐怖が高まり、冷戦が終わると歯止めのない競争社会が価値やモラルを相対化しはじめた。そんな不穏な世紀末に、欧米の近現代の激動を生き延びたカトリック教会が新しい形で「希望」を説いていることに救いを感じて、時間の流れが違うヴァティカンや、東欧出身のヨハネ=パウロ二世の活躍を紹介することができた。
けれども、新世紀が始まるとすぐにアメリカで同時多発テロが起き、経済格差の広がる世界で暴力がはびこり戦争が次々に起こった。そんな時に、突如としてドイツ人法王を登場させたカトリック教会の新機軸にまた感心して、ベネディクト一六世に至る新章を加えたのが、中公文庫版だった。そのベネディクト一六世がまさかの生前退位を表明して、アルゼンチンのベルゴリオ枢機卿がフランシスコ法王となり、その率直さと謙虚な人柄と親しみやすさでまたたく間に世界中の人気者になった。それだけではない、環境破壊における先進国の責任を指摘することを恐れず、ぶれない正論を堂々と発し続けたのだ。(…)今回の角川ソフィア文庫版では、そんなフランシスコの足跡をたどる新章を付け加えることで、もう一度希望のメッセージを届けたいという思いがかなった。
というわけで、ブログでは継続して書いてきた今世紀のローマ法王についてアップデートしたのだけれど、今回の角川版は最初から、2019年11月のフランシスコ教皇訪日に合わせて提案していただいたものだ。おかげで、オンラインニュースにいくつも取り上げてもらうなど、今までにない展開があった。
https://president.jp/articles/-/30840
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/6853
https://bunshun.jp/articles/-/15745
アクシデントもあった。
教皇訪日直前に、外務省がこれまでの「ローマ法王」という呼称を「ローマ教皇」に変更したというのだ。
「教皇」というのは1981年のヨハネ=パウロ二世の訪日以来日本のカトリック会は正式に使ってきた言葉だけれど、外務省には外交樹立以来の「ローマ法王庁」という名が残っていて、一般メディアでは「法王」が使われていた。私は個人的には、「教皇」を使っていたけれど、本のタイトルなどは「ローマ法王」に合わせていたので、「ローマ」の後に続くときは「ローマ法王」、単独なら「教皇」、フランシスコ教皇、などと使い分けていた。でも、出版物では基本的に出版社の判断に任せていた。
語感としては「ローマ法王」の方が「ローマ教皇」よりも、発音した時に口を閉じる回数が少なくて好みだった。
もともと漢字としては「王」より「皇」が格上で、だから日本古代の「大王」は中国の「皇帝」に対抗して「天皇」と称するようになった。で、今でも、外国語訳としては、イギリスやベルギーだのの「王」はキングと呼ばれ、日本の天皇はエンペラーと呼ばれている。エンペラーは帝国主義を連想するから微妙なのだけれど。で、出家した「上皇」は「法皇」となるし、それ以外の仏教の長老は「法王」となるなどの使い分けがあった。
それを応用した「ローマ法王」という訳を、「王」よりは「教え」を、と日本のカトリック教会が「教皇」に変えたわけだけれど、漢字的には、「王」が「皇」に「格上げ」されたとも言える。そうなると皮肉だ。
実際ローマ・カトリック内の正式の呼称にはヨーロッパの王侯貴族と同じ尊称がきっちり決められていて、パレスティナで処刑されたイエス・キリストが聞いたらびっくり、という恭しさが中世以来続いている(今回の日本でも「台下」などと書かれていた)。でも、その他に、より「キリストの教え」に近い「奉仕者」「仕える人」という表現もあって、ヒエラルキーのトップには必ずそれを適用する修道会などもある。まあ、呼び名などは関係なく、「仕える姿勢」が問題なのだけれど、世間には肩書や呼ばれ方で自分が「偉い」と錯覚して他者を見下したり蹂躙したりしてしまう人も少なくないから、指導者にこそ「謙虚さ」は絶対に必要だ。
日本のカトリック信徒は「パパさま」と呼んでいるのが普通のようだ。
「教皇様」というよりは親しみがあるけれど、「パパ」も「さま」も、いろんな意味でこの場合の日本語になじまないなあと思うので、私にはとても発語できない。司祭だって「神父」と「神」がついているし。それにたいていは神父「さま」と呼ばれている。フランス語ではフランシスコ教皇は「フランソワ」と呼ばれるし、教皇は「Papeパップ」で、普通の言葉でないし、神父は「Pèreペール=父」、(家庭内での父親の呼称はパパが一般的)。(ついでに言えば、フランス語では、報道などでフルネームを言えば、敬称はなくてもいい。 たとえば、エマニュエル・マクロン、と言えば、大統領とかムッシューとかをつけなくてもいいのだ。)
日本語では、この敬称の使い方でその後の話の枠が決まってしまうので、聖職者たちとはフランス語の方がずっと話しやすい。でも日本のシスターたちとは、特に「シスター…」と言わなくても普通に「・・・さん」と呼べるので話しやすい。
と、まあ、このコメントは「ローマ法王」(法王でも間違いではない、と外務省は言っている)というタイトルをめぐっての雑談となりました。教皇訪日をフランスから中継やビデオ視聴して思ったことは私のブログ(2019年11/24-25)に書いたのでどうぞ。
文庫判 272頁 定価 本体800円+税
出版社: 角川ソフィア文庫
ISBN : 9784044005207
ジャンヌ・ダルク 超異端の聖女

痛快で、やがて悲しい—。
ジャンヌ・ダルクの生涯を一言であらわすならば、このようになるでしょうか。
講談社サイトより
時は15世紀、英仏100年戦争の末期。フランスを二分する未曾有の国難のなか、パリを追われた失意の国王シャルル7世のもとに彗星のごとくあらわれたのが、ジャンヌ・ダルクです。甲冑を身にまとい馬上の人となった彼女は破竹の勢いで敵方を打ち破り、またたくまにシャルル7世をランスでの戴冠に導きます。しかし華々しい栄光もつかの間、ジャンヌはイギリス軍に引き渡され、異端者として生きたまま火あぶりにされてしまうのです。「声」に導かれるまま生まれ育った村を旅立ったのが16歳、火刑台に立たされたときには19歳でした。
本書は、100年戦争の政治的背景から、中世におけるお告げや聖女の系譜など、彼女が生きた当時の世界を浮かび上がらせることで、ジャンヌ・ダルクの全体像をあざやかに、しかも親しみやすい筆致で描きだします。
名もない羊飼いの娘だったジャンヌを突き動かした「声」、ついにはシャルル七世をも動かし、フランスを熱狂させたものとは、いったい何だったのでしょうか。カトリックの聖人は数多くいますが、異端者として火刑にまでなりながら、500年後に聖女として認定されたのは彼女だけです。「普通の女の子」が国を救い、国家意識を創ることを可能にしたヨーロッパ中世とは、そして彼女を「守護聖女」として今なお現役で生かしているフランス人の心性とはいったいどのようなものなのでしょうか。異端にして聖女、華やかで苛烈なジャンヌ・ダルクの世界に、あなたも飛び込んでみませんか?(原本:講談社現代新書、一九九七年)
【本書の内容】
プロローグ
序 章 ジャンヌ・ダルクとはだれか
第1章 ジャンヌ・ダルクの先駆者たち—カリスマと聖女
第2章 神の「声」を聞いた少女
第3章 中世の政治と宗教—少女戦士はいかにして誕生したか
第4章 戦場の乙女
第5章 ジャンヌの最期
エピローグ
あとがき
学術文庫版あとがき
おもな参考文献
A6判 224頁 定価 本体960円+税
出版社: 講談社学術文庫
ISBN : 978-4-06-516276-7
渡り鳥の見たキリスト教

日仏間を飛び回るバロック音楽演奏家が快刀乱麻、縦横に語り尽くすー
カトリック教界の「今」と、目からウロコの比較文化・社会論の全て。
著者のコメント
この本は私にとって、とてもありがたい本だ。
さまざまなブログを書くようになってから、その中には閉鎖、削除したものもある。
記録として保存することを目的に書いたブログについては、最初は便利だと思っていたけれど、その量が増えていくにつれて、なんだか情報を切り取ってスクラップブックに入れてから閉じてしまう、あるいは存在も忘れた「積ん読」本のようになっていく気がした。一方で、頭の中の情報のネットワーク自体はどんどん複合的になっていく。ある日キャッチしたある情報は、あっという間に素材としてレシピに組み込まれてしまい、「素材の名前の覚書」のつもりで書くブログが新レシピの開発の覚書になってしまって、長くなり、時間がとられる。
ブログと自分自身の関係性がよく分からなくなっていた。
とはいっても、実名のサイトやブログは、その「サービス精神のなさ」にかかわらず、私の本の読者さんたちからの貴重なアクセスがあるので、少しでもお役に立てれば、という気も働くし、すぐには著述できない情報やフランスの情報を伝えたいという思いもある。
ネット上には私がほぼ毎日のようにアクセスするブログもある。実名の方もいれば、どこのどなたかは分からないけれどすばらしい情報量と分析力で感心させられるものもある。
子育てや猫との暮らしや日常情報の発信で魅力的なブログもたくさんあるし、その中には「ブロガー」として生計を立てることができる人もいれば、ブログの書籍化でデビューする人もいる。
私のこのブログの場合はその反対で、書籍には書けないこと、書けなかったこと、まだまとまっていないこと、いつか使える新情報や考察などの積み重ねだから、基本が一人語りであり、コメント欄も設けていない。
「想定読者」がないので、各テーマについて専門事項を詳しく解説してはいないし、そのテーマの「専門家」や「好事家」でなければ理解不可能、長すぎ、意味が分からない、という記事もあることは承知している。
「読者を増やす」というタイプの工夫はゼロだ。
でも年月が経つにつれて、ばらばらの記事の起伏の中に、いろいろな潜在的な運動量が蓄積されていることに気づいていた。
今回はその中の「カトリック・ウォッチング」を中心に取り出して編集していただいたので、その「方向性」や「効果」が実感できて嬉しい。
この本のフランス語のタイトルはブログのタイトルと同じくL’art de croireだ。
私は自分のほとんどの本にフランス語のタイトルを入れている。日本語のタイトルの訳ではない。(フランス人が手に取った時に、誰が何について書いているのか分からないと困る時を想定している。)
フランス語のタイトルの方がすんなり頭に浮かぶ。このL’art de croireもそうだった。これを書いている時の私の姿勢にぴったりだ。このタイトルをすばらしいと言ってくれたのは日本語の読めるベルギー人の神父さんだけだ。この意味に込めたいろいろなニュアンスをまとめて分かってくれたのだと思う。これを訳すことは私にもできない。
仮想空間に書いたものをいつまでも溜めていくことに不安を覚え、ブログをまとめて一冊の本にするというブログサイトのサービスを利用しようかと考えたことがある。でも、編集するような余裕はないし、ただ年代順に並べるだけでは、ネットで検索するのとそう変わりはない。今回この本が完成して、その爽やかな表紙を見て、あらためて感謝の気持ちでいっぱいだ。
どんなにネットで読む時代になっても、「紙の本」の「そこにあって手に取ることのできる」ありがたさは変わらない。今私がこれを書いているPCのすぐそばに、読みかけの本が重ねて開かれている。90代の日本人男性がパリに残した蔵書の中の『梅原猛全対話3 仏教を考える』というぶ厚い本と90代のフランス人女性に譲られた蔵書の中の詩集だ。出会ったこともない二人の傍にあったこの2冊がモノとモノとして私のそばで触れあっている。
その時、モノはコトになる。
新書判 並製 352頁 定価 本体1500円+税
出版社: フリープレス社
ISBN-10: 443425569X
ISBN-13: 978-4434255694
カトリック・サプリ4 日々の生活に気づきをもたらす25の話

文化評論家として、執筆家として、音楽家として、さまざまな視点からエネルギッシュに発信し続ける著者の、人生を豊かに生きる秘訣。
あるときは世界の経済に目を向け、あるときはテロリストの犠牲となった修道者の魂に共鳴し、またあるときは目の前の幼い子どもたちや年老いた愛猫に心を寄せる。「政治も宗教も、共通善もペルソナの尊厳も、すぐそばにいる他者への小さな配慮なしには、きっと、なんの意味ももたない」という著者の思いは、私たちの日々の生活の中に、大切な気づきをもたらしてくれるだろう。
〜 編集部からひとこと 〜
常にポジティブに人生を見つめ、やさしさと丁寧な気遣いにあふれる言葉の数々。今日までの自分を見直し、これからの生き方を考える大きな力を与えてくれる一冊です!
目次
はじめに 三澤洋史
その1 魂の求めるものに気づくとき
明鏡止水
天使の名前
二十一世紀の聖骸布
聖人と出会うこと
音楽とコミュニオン
その2 日常の中に見つける宝
家族
贈り物
病めるときのインターネット
看取りと復活
私が幸せなとき
その3 現代社会の中で思うこと
招かれるのは誰なのか
「子どもを愛する」とはどういうことか
フランスの教会テロの後で思うこと
あるジャーナリストが知りたかったこと
キリスト者と政治
その4 忘れてはいけないこと
教育者に必要なもの
ゆるす、忘れる、続ける
死後の世界はありますか
神は向こうからやってくる
光あれ
その5 聖なるものと出会うとき
奉献生活とは何か
戦後七十年と聖女ジュヌヴィエーヴ
マザー・テレサの逆説
ジャンヌ・ダルクと神学
復活考
新書判 並製 205頁 定価 本体740円+税
出版社: ドンボコス社
ISBN978-4-88626-641-5 C0216
神と金と革命がつくった世界史

キリスト教と共産主義の危険な関係
偶像崇拝なくして歴史はつくられなかった。
「普遍」を標榜する神と金と革命思想は、理想を追求する過程で偶像化され共闘や排斥を繰り返す。壮大な歴史から3すくみのメカニズムを解明する。
著者のコメント
この本は、神・カネ・革命の3Kの危険な関係について考えてきたことをまとめたものだ。
これを一度きっちりと「総括」しておかなければ、次のステップに進めないと思ってきた。
明治維新から何年とか、戦後何年とかいう懐古的な語りが、いろいろな思惑と共に繰り出される一方で、歴史の改竄や憎悪や警戒心の醸成によって、本当の「平和」への感性がどんどんと鈍っていくような焦りをおぼえるからだ。
この本を書くことで、今まで発信してきたことへの自分のスタンスや、現在世界や東アジアで起こっていることを考えることの基盤が意識化されたので、自分にとっても必要な過程だったと思う。この本を読むことで同じように、世界の見え方がよりクリアになるという読者がいれば嬉しい。
このタイトルで「革命」というのは、近代革命とマルクス主義革命における非民主主義的な暴力による主流秩序の否定を念頭においてはいるけれど、広い意味では、他者を支配する「力」を意味している。
世界の各地で伝統や文化や自然観がばらばらだった時代から、交通、通信の発達で、世界中がつながってしまった時代において、それぞれの共同体の「価値観」の違いが露わになったにもかかわらず、「強いもの」が「弱いもの」を支配しようとする覇権主義は止むことがない。
「神」はどこでも支配者に利用されてきた。
一神教の神は本来ならば全ての被造物の創造者なのだから、被造物の平和な共生を促してもいいようなものだけれど、実際は、一部の権力者や一部の民族や一部の文明の覇権を正当化する道具になってきた。
「西洋近代」はそんな「神」から自立していく歴史のように思えたけれど、「神」にとって代わるはずだった「理性」は、生産合理性を正当化する道具になった。
今や、むき出しの「力」が人々を分断し、被造物である全自然を破壊する恐れが叫ばれている。
気がつくと、「神」の座には「カネ」(富・資本・金融)の論理が陣取っていた。
思えば、社会の主流秩序を決定する人々はいつも、「聖なるもの」や「力」を恣意的に分節しながら加工して「ストーリー」を作ってきた。始まりには、「カネ」にだってストーリーがあった。その一つの到達点が「西洋近代(モダン)」だったけれど、「ポストモダン」がこのストーリーをことごとく壊してしまった。
「近代」の指標だった「理性」は方向性を失った。価値相対化によって、「何も信じない」ことは、「なんでも信じる」こととセットになってしまったのだ。ストーリーは壊れても、ストーリーを補強していた偶像は残る。カルトもオカルトもヘイトもそこで養われる。
だからこそ、権威付けとしての「神」も、力とカネのあるところにはまだまだ生き残っているのだ。
でも、力や金を担保にしなければやっていけない「神」なんていらない、とつくづく思う。
偶像化し、覇権主義や功利主義におかされない「神」を養うのは「愛」だ
と、宗教者は言っている。
「愛」!
「愛」は、残念ながら、力にもカネにも負ける。
でも、「愛は死よりも強し」と言われるように、「愛」は「死」にだけは、「勝つ」。
「力」も、「カネ」も、「死」には負けるというのに。
この本のタイトルには「愛」という言葉がない。
「神」と「カネ」と「力」の三者のバトルの中で見えてこないものを、私たちは、どのようにすれば、見ることができるのだろうか、見せることができるのだろうか。
280頁 2700円+税
出版社 : 中央公論新社 (2018/9/10)
ISBN : ISBN978-4-12-005114-2
キリスト教は「宗教」ではない

自由・平等・博愛の起源と普遍化への系譜
本来、「生き方マニュアル」として誕生した教えから、受難と復活という特殊性を通して「信仰」が生まれた。「宗教」として制度化したことで成熟し、広く世界に普及する一方で、様々な思惑が入り乱れ、闘争と過ちを繰り返すことにもなった。本書は、南米や東洋での普及やその影響を通じて、ヨーロッパ世界が相対化され、近代に向かう中で、「本来の教え」が普遍主義理念に昇華するまでの過程を、激動の世界史から解読する。
著者のコメント
長崎県の五島出身でノンフィクション作家の今井美沙子さんが「恩師」である福江教会の松下佐吉神父について語ったものに、努力すべきは、まずよき人間であること、次に、よき社会人であること、最後に、よきカトリック信者であることのために努力するようにという言葉があった。
まずカトリック信者であるならばカトリック信者としての物差しで計って、人を批判する材料になりがちである、まず良い人間であるよう努力し、次に社会人としての責任を果たすことがカトリック信者の物差しで「良き信者」になることに優先する、というものだ。
この三つは、私がこの新書で語った
「ひとりひとりの生き方としてのキリスト教」
「イズム(共同体の規範)としてのキリスト教」
「宗教としてのキリスト教」
に重なる。
「カトリック教会」の教義や典礼というのは歴史の文脈の中で生まれた「宗教」であって、その遵守を第一の指針として生きていくべきではないと松下神父は言っているわけだ。カトリック教会、という「宗教」のシステムの中でキイとなる立場の「司祭」である神父にこう言わせているところが、「良き人間とは何か」という問いであり続けるキリスト教の底力だなあと思う。
この本を書いた後で、この「宗教ではない」というタイトルが挑発的に聞こえるのではないかと少し心配して、知り合いのカトリックの司祭やカトリック雑誌の編集者などに話したことがある。みな拍子抜けするくらいに「ああ、いいですね」と言ってくれた。でもよく考えたら、教義や典礼は時と共に成立し、キリスト教世界でも時と場所によって多くのヴァリエーションがあるのだけれど、彼らが「クリスティアニズム」(キリスト教、キリスト主義)と自覚しているベースには、「宗教」とは別の、「いかに生きるべきか」というのがあるのだなあと再確認した。
一方で、いわゆる、「キリスト者」ではないある人からは、「護教的」だと言われた。これも意外だった。私は「宗教」としてのキリスト教やカトリックが「正しい」と言っているのではないからだ。
それでもこの本の中でカトリック教会の誕生と変遷が一つの導線になっているのはいくつかの理由がある。
日本を含む今のグローバル社会の「先進国」スタンダードが、過去にローマ帝国の版図に広がったローマ・カトリック教会の影響を正逆の方向性はあっても、ほぼそのまま受け継いでいるからだ。
プロテスタントの誕生も、近代革命も、政教分離も、不可知論や無神論さえも、ローマ・カトリック教会がケルト人やゲルマン人らの「蛮族」をまとめて今の「ヨーロッパ」を形成した基盤から生まれた。
私は、プロテスタントとの宗教戦争の後でカトリックを政治的に選択した「カトリック文化圏」フランスに住んでいる。そのフランスは、また、近代啓蒙思想の中心地のひとつでもあり、革命によって、プロテスタント諸国よりもはるかに世俗的な社会を築いてきた。しかも中央集権的で中華思想の強い国柄なので、何層にも複合する「物語」を何度も語りなおしたり創りなおしたりという跡が比較的よく見える。
それは、地政学的な共同体であるフランスを「普遍主義」の国として語ることの営為だ。そこに「無理」があったり「欺瞞」があったり「粉飾」があったりするのは当然だけれど、この「普遍」(「カトリック」は普遍という意味でもある)は、この国に住む日本人(しかも女性で今やシニアという弱者要素満載)である私にとってとても快適な「建前」であり続けた。
「愛国、忠誠、勇気」などが国是の国ではなく、「自由、平等、博愛」という「普遍」看板が掲げられている国だからこそ、マジョリティの白人であろうがマイノリティの人たちであろうが、いっしょにフランス・バロック音楽を語ったり演奏したり教えたりさえすんなりとできてきたのだ。
その意味で、私は「普遍主義」の恩恵を受けてきた信奉者だから、その「建前」としてのフランスやカトリックに対して「護教」者であることは認めよう。
その「普遍という建前」が「フランス」という「国」や「カトリック」という「宗教」の枠内に閉じ込められない「本来」の意味を指している限りにおいて。
224頁 800円+税
出版社 : 中央新書ラクレ (2017/10/6)
ISBN : 978-4-12-150597-2
ナポレオンと神

世界は驚愕し、民衆は夢を抱いた。
夢を現実化する革命児か、はたまた新たな抑圧を企てる独裁者か。神たろうと世界史の中心舞台に躍り出た、ナポレオンの叡知と野心。権力・宗教間の苛烈な暗闘の淵から浮上する、ヨーロッパ精神の核心を活写する。思想史研究の新地平。
著者のコメント
百日天下の後で敗れたナポレオンの運命について不思議なことがいくつもある。
その一つを挙げよう。
彼がいったん逃げてから捕らえられて、イギリス軍の手に渡ったところはジャンヌ・ダルクの最後のことさえ思い出させるが、二人の大きな違いは、ナポレオンが一度も「法廷」に引き出されなかったことだ。ジャンヌ・ダルクが異端審問の記録によってラテン語訳とはいえ、詳細な「肉声」のディベートが伝えられているのに対して、ナポレオンはあっという間にイギリスの軍艦ノーサンバーランド号に乗せられてものものしい護衛艦もつけられて大西洋の孤島のセント・ヘレナに流されてしまった。
そのことについて歴史書はみな、それはイギリスがナポレオンをロンドンに連れてこられた場合に、「Habeas Corpus」を申し立てられて亡命を願い出る可能性を封印するためだったと書いている。
Habeas Corpusとは「Habeas Corpus ad subjiciendum」の最初の部分で、法廷に被告を引き出す時の決まり文句である。
ナポレオンはフランスで譲位の手続きをしたのだからそのままフランスに残っていたとしたら助命された確率はどのくらいあっただろう、船でアメリカに行くのではなく、地続きでイタリアに逃れることはできなかったのだろうか。
流刑なら暗殺されるよりも延命ができたのだろうか。
ローマ教皇ピウス七世による助命願いはどのくらいの効果があったのだろう。
疑問は尽きないが、この部分は結構タブーの領域になっている。なぜだろうと思っていたが、要するに、三権分立や法治国家の先駆だと自負していたイギリスやフランス共和国にとって、ナポレオンのように突然エルバ島から脱出して皇帝に返り咲いたような不都合な「例外」をどう扱っていいかわからず、
確たる法的手続きなしに「世界の果て」に追いやってしまった事実は、恥ずべき事であったと自覚していたからだろう。
それでも、この時代のヨーロッパ以外の地域でこのようなケースがあれば、ナポレオンのような失墜者はそれこそ即殺害されるか処刑されるかで闇に葬られるだろうから、イギリスの処置は、「文明国」にとってせいいっぱいのかっこうづけだったといえる。
もう一ついつも不思議なのは、「ナポレオン」という名前だ。
姓のボナパルトではなくて、ブルボン朝などに倣ってナポレオン王朝を創始したかったのは分かる。無理に「聖ナポレオン」を創作して自分の誕生日を聖ナポレオンの祝日に変えてしまったという話はよく知られていて、その経緯も分かっているのだけれど、ナポレオンという名は、カトリックのボナパルト家の次男の洗礼名なのだから、もともとゆかりの聖人がいたはずではないだろうか。
歴史的に有名なのは、1263年ローマ生まれで、ニコラウス三世の弟の息子であったナポレオン・オルシーニという人がいて、アヴィニョンでベネディクト12世側近の枢機卿として1342年に死んだと記録されている。ナポレオンの生まれたコルシカは長くイタリア領だったから、地元では十分あり得る聖人名だった可能性があるわけだ。けれども少なくともナポレオン・ボナパルト以降のフランスでは、新しい聖人が当てられた。
ナポレオンの兄弟の名前はジョゼフ、リュシアン、ルイ、ジェロームなどよくあるものだ。最初がイタリア風の綴りや読み方だったとしても簡単にフランス風に変えられただろう。
父方の祖父の弟らしい人にアジャクシオの政治家で1717年生まれで、1768年にフランス軍に殺されたというナポレオーネという人がいる。 ナポレオンはその翌年に生まれているから、その人の名をつけられたのかもしれない。それとも、ミラノにモンテナポレオーネ通りという高級ブチック街があるから、もとは土地の名なのだろうか。
なんにしても、コルシカがフランス領となり、海を渡ってフランスに留学した息子たちの中で彼だけがフランス人にとってなじみのない名を持っていたわけだ。
でも、もし彼の名がジョゼフとかジャンとかであったら、また革命で処刑されたルイ16世と同じルイなどであったとしたら、彼の世界観、覇権主義の視座が別のものになっていて、歴史は変わっていたかもしれない。
なんとなくジャンヌ・ド・シャンタルのことを思い出す。『聖女伝』で紹介した彼女は、フランソワ・ド・サル(サレジオ)と共に「聖母訪問会」を創設したジャンヌ・ド・シャンタルは死後に聖女となったけれど、ジャンヌという名(ジャンすなわちヨハネの女性形)はジャンヌ・ダルクをはじめとしてあまりにもたくさんあるので、聖ジャンヌとは呼べず、聖ジャンヌ・ド・シャンタルと呼ばれていたのがいつの間にかシャンタルが通称になり、聖女シャンタルとして苗字が洗礼名として使われるようになった。シャンタルという新鮮な女性名は一時期のフランスでとてもポピュラーなものになった。ブルジョワではマリー=シャンタルなどという合成名によく使われた。
ナポレオンという名の人には、会ったことがない。
この『ナポレオンと神』にはいくつかの思い出も重なる。
1978年に国際交流基金でパリ大学に特別講義に来た島田謹二先生のことだ。
東大の比較文学の創始者で当時77歳だったから、大学側もとても丁重に迎えて、東大の比較文学の博士課程に籍をおいていた私に特別に声がかかって、講義に出てくれと言われた。
島田謹二といえば私の中で英米文学者のイメージだったが、フランスの英文学者についても研究していて、フランス語も自由に読めて多くの詩を暗唱していた。けれどもフランスに来たのはそれが初めてで、フランス語の聞き取りや会話には通訳が必要だったのだ。
この島田先生がリールの英文学者の文献を探すのを手伝ってノール地方を案内することになった。いろいろお話しするうちに、彼がナポレオンの大ファンであることが分かり、フォンテーヌブローからワーテルローまでいろいろなところにご一緒した。その時の思い出を彼も後に『英語青年』という雑誌に書いて送ってくれた。
「ナポレオン巡礼者」の熱い思いを見るのは初めてで、しかもそれが日本人の英文学者であることに驚いた。
私がポーの詩のファンで『アナベル・リイ』が特に好きで人形にもその名前をつけていると言うと、『大鴉』の訳本を献呈してくださったのも懐かしい。
『ナポレオンと神』は『ジャンヌ・ダルク異聞』に続いて白水社の『ふらんす』に一年間連載したのだが、事情があって単行本化できなかった。どうするか迷っていた時に、『ユリイカ』の増刊号のエリック・サティ特集に記事を書いてくれと青土社から依頼が来た。青土社の『ユリイカ』はもう20年以上も前にクロソフスキー特集の記事を書いて以来で、『現代思想』や『イマーゴ』などいろいろ書かせてもらった。亡くなった編集者の津田新吾さんに日本でワープロを借りたりおうちで手料理をごちそうになったりしたこともある。
21世になって初めての青土社との再会となった『エリック・サティ』の後でお会いした編集者にナポレオンの話をしたらすぐに興味を持ってくださったのだった。
『ナポレオンと神』は、青土社から18年ぶりに出す単行本となる。インターネットの普及によって出版業界も大きく変わったが、古巣に帰ったような懐かしい気持ちで感慨深い仕事となった。
256頁 2600円+税
出版社 : 青土社 (2016/11/11)
ISBN : 978-4-7917-6949-0
単行本 キリスト教の謎 奇跡を数字から読み解く

一神教、三位一体、七つの大罪、十戒、十二使徒、十三日の金曜日など、1から13までの数字が象徴する奥義を解読。史学・神学・心理学・美学・社会学などの観点から多角的に分析。
著者のコメント
この本には「奇跡を数字から読み解く」という副題がついている。
「数字から」という発想は、以前から、キリスト教を語るには「一神教」と「二元論」と「三位一体」
という「一、二、三」から始めなければならないと考えていたことに由来する。
後は、数字に合わせてキリスト教のコンテンツや関連事象について風呂敷を広げてみたわけだけれど、
これらのコンテンツを合わせても、それがキリスト教だというわけになるわけではもちろんない。けれ
ども、「一、二、三」のキリスト教がなければ、この本で紹介した諸々の事象は何一つとして起こらな
かった。
「奇跡」というのは「奇跡の治癒」や超常現象という意味での奇跡ではない。ローマ帝国の属領だった
ユダヤ人の国で二千年前に生まれたキリスト教が普遍宗教として成立し、分裂し、進化し、増殖し、ヘ
レニズム世界を席捲するほどに有力な宗教となって、最初の「一、二、三」から限りなく遠くなったの
にも変わらず、原型記憶と復元機能を発動して生き延びたこと自体の驚きだ。
キリスト教美術のインパクトにもあらためて感慨を深くしている。
神々や怪物や超自然の表現は古今東西の文化においてそれぞれ個性的なものが存在するけれど、「人間
」、正確に言うと「苦しむ人間」の表現については、「人となった神が苦しんで殺された」という場面
を繰り返し強迫的に描いてきた西方教会の文化が突出している。
人が生前の悪行のせいで地獄に落とされて苦しむというタイプの図像はどこにでもあるけれど、イエス
の受難を通して、無実の罪で苦しめられる男やその死んだ息子を抱きかかえて悲嘆にくれる母の姿など
が微に入り細に入るリアルな形で繰り返し描かれてきたというのは考えてみると人類の美術史における
途方もない出来事だった。
近代以降の世界では、この「奇跡」の舞台となった「西洋」の国々が「覇権国」として地球の隅々にま
でその文化を伝播した。そのせいで、人の内面を表現するタイプの具象美術もまるで普遍的なもののよ
うに感じるけれど、キリスト教なしには今のような形ではあり得なかったとつくづく思う。
いわゆるキリスト教文化圏の国々ではそのような特殊な表現がデフォルトになっているので気づかない
けれど、日本のような国の文化を継承している人々がキリスト教由来のさまざまな事象を自分のものと
できることの豊かさはかけがえがない。
この本をこういう形で読んでいただけることを可能にしてくれた関係者に感謝します。
256頁 2600円+税
出版社: 中央公論新社
978-4-12-004845-6
カトリック・サプリ3 人生に希望の種を蒔く25の話

比較文化史家・バロック音楽演奏者として活躍中の竹下節子氏が、世界情勢から人々の心の動きまでに思いを馳せ、「『いのち』の光を一人ひとりが輝かせ、分け合い、怖れずに進む」ことを促す好評エッセイ集の第3巻!
目次
序にかえて……岡田武夫
その1 アンテナを広げよう……私たちは何を傾聴するのか/聖書の不思議な数字/喜びのボランティア/人生はホスピタリティー/いのちの水とのつき合い方
その2 求め、受け入れ、差しのべる……カトリックをサプリにするわけ/日常の中の祈り/人生とアイデンティティー/貧乏について/ハンディとともに生きる
その3 信念と選択によって、すべてが変わるかもしれない……リタイアの仕方/イエスと友達になれるだろうか/ユーモアの生む力/最大の贈り物/災害の後
その4 逃げずに向き合う中で、出会うものがある……十字架のキリスト/ユダが「裏切り者」になったわけ/尊厳死と孤独死/エコロジーと動物の権利/出会いについて
その5 進み続けるかぎり世界は広がる……人事と天命/マリアは読み続ける/神の国の地図/宇宙に神を見る話/永遠のいのち
新書判並製 205頁 定価 本体740円+税
出版社: ドンボコス社
ISBN978-4-88626-603-3 C0216
フリーメイスン もうひとつの近代史

謎めいた存在ゆえに、陰謀論の格好の対象となるフリーメイスン。
秘密に包まれたイニシエーションの実態とは?
「自由、平等、兄弟愛」などキリスト教ルーツの価値観を政治から切り離し、
「普遍価値」として復権させることが彼らの使命である。
アメリカ独立戦争、フランス革命から『シャルリー・エブド』事件まで、フリーメイスンの誕生と変容を辿りながら、西洋近代をもうひとつの視点からとらえなおす。
著者のコメント
2001年に『グノーシス 陰の精神史』(岩波書店)という本にグノーシスとフリーメイス
ンについての項を書くように頼まれた。その記事に興味をもってくれた編集者から、フリ
ーメイスンでぜひ一冊書いてみないか、と声をかけられた。もし無理なら監修という形で
共著でもいいと言われたが、日本でいったい誰がどんなことをフリーメイスンについて書
けるのか分からなかったのでそのままになってしまった。
その後、『無神論』(中央公論社)、『陰謀論に騙されるな』(ベスト新書)などによ
って、ヨーロッパの精神史を比較宗教とは別の角度から俯瞰する作業を重ねてきた。その
流れから、近代史の中でいつも独特の位置を占めているフリーメイスンについてようやく
一冊の本にまとめる機会がやってきた。
その間に、インターネットの世界が際限なく広がり、「好奇心」によってフリーメイス
ンを知りたい人は誰でも簡単に膨大な「秘密」にアクセスできる時代になった。けれども
手軽に消費できる「秘密」は時として「本質」を見失わせるし、「陰謀論」だけがウィル
スのごとく広がる。
一方で、実はメンバーの匿名性以外にはもはや「秘密」が意味を持たなくなりかけてい
るフリーメイスンのメンバーたちは、それぞれのロッジ(会所)での研究発表やそれに続
く議論をインターネット上で発表するようになった。匿名性が普通に通用するウェブ空間
はフリーメイスンの活動と相性がいいのだ。今までは内部の会報でしか知ることのできな
かった情報に触れることができるだけでなく、会員たちの「本音」も伝わってくるように
なったのだ。
私が追っているのはフランスのフリーメイスンのサイトや掲示板がほとんどだ。そこで
は、陰謀論だの秘密結社だのという言葉とかけ離れた議論が繰り広げられている。
冷戦後、アメリカの一人勝ちで世界を席捲したグローバルな新自由主義によって経済格
差は拡大した。その後、近代社会のスタンダードである民主主義を規範としない中東や中
国などの「非キリスト教文化圏」が台頭する中で、マネーがすべての基準になるかのよう
な空気が生まれている。その結果、多くの「普通の人」が一種の「生きづらさ」を抱える
ようになり、その一部は内向きに引きこもったり攻撃的な排他主義に向かったりすること
もある。そもそも近代の西洋が唱えて押しつけた「普遍主義」など普遍でも何でもない、
民族固有の伝統的価値観に回帰するべきだ、という声が聞こえてくるようになった。
けれども、例えば日本の目から見る「欧米の価値観」は別にキリスト教文化圏における
固有のもの、伝統的なものではない。むしろ固有の価値観や伝統が崩れたり内部で対立し
あったりを繰り返す中で、絶え間ない戦争や革命などの大きな代償を払いながら、「伝統
」や「宗派」の違いを超えて「共生」することを目指して少しずつ培われてきたものだ。
ヨーロッパのフリーメイスンはその土壌の一部をなしている。プロテスタントのイギリ
スで生まれた近代フリーメイスンは、「啓蒙」の世紀に模索された自由平等主義の息吹の
もとでカトリックの絶対王権下のフランスにも広がった。
世界的に見ると、今のフリーメイスンには政治や宗教に口を出さない社交クラブ、人脈
作りの場となっているものが多い。フランス最大のメイスナリーである「フランス・グラ
ントリアン」はそれらと一線を画するものだ。「政教分離(ライシテ)」の牙城として、
社会民主主義寄りの政治ロビーのひとつとなっている。現在の首相であるマニュエル・ヴ
ァルスは1989年から2005年までグラントリアンのメイスンだった(2003年頃から会合に
出席しなくなって、2005年に正式に脱退した)。彼の政治家としての足掛かりとなったエ
ヴリィ市長の職も、2001年に同じフリーメイスンである前市長の後を継いだ形で獲得して
いる。
とはいっても今の内閣にメイスンを多く起用しているわけではない。フリーメイスンの
方も、政治家たちが敢えて言えないようなメッセージを発信する方向を目指しているよう
だ。世代的には今や68年5月革命世代(日本でいうと団塊の世代)の兄弟団の体をなして
いるものもある。この世代は伝統宗教から離れて無神論や共産主義に近づいた人が多いの
で、革命の夢が消えた後で共同体意識を求める心がフリーメイスンに向かったのかもしれ
ない。
フランスのフリーメイスンは、フランス近代史を語る時にまったく新しい視座を与えて
くれると言えよう。2015年1月の「シャルリー・エブド事件」も、フリーメイスンの歴史
を通して見ると、単に「宗教を揶揄するのはいかがなものか」などという感想と別のもの
が見えてくる。
私は啓蒙時代のフランスの普遍主義の模索のひとつの形として結実したフランス・バロ
ック音楽を演奏している。特に、道半ばで病に倒れて活動を中止したせいで忘れられてし
まったシャルル=ルイ・ミオンという作曲家の残したオペラのダンス曲などを研究してい
るのだけれど、これまでにミオンについて自著の中で触れたのは『バロック音楽はなぜ癒
すのか』(音楽之友社)でだけだった。今回の『フリーメイスン』の中でふたたびミオン
に言及できたことに感慨を覚えている。
もちろん人間が複数集まるところ、個人のエゴイズムの対立や嫉妬、欲望など、多くの
「人間的なもの」が渦巻いて、当初の理念からの逸脱や堕落、退廃、不正などが起こるこ
とはフリーメイスンでも同様だ。とはいえ、複雑に広がるフリーメイスンのネットワーク
の構造は、内部の個人や派閥や組織の一部が「病んだ」時に、欠けたものをどこかでバッ
クアップしたり、新陳代謝を可能にしたりする柔軟性を全体として備えているようにも思
える。
外部のものを排除する秘密結社というイメージのフリーメイスンを、それとは反対の普
遍主義の文脈から眺める新鮮さをこの本でぜひ味わっていただきたい。
256頁 1650円+税
出版社: 講談社選書メチエ
978-4-06-258604-7
カトリック・サプリ2 生き方をインスパイアする25の話

人生の歩みの中で出会う様々な出来事を多角的に分析し、思いもかけないメッセージを紡ぎだす竹下ワールドへの扉を開けてみませんか。
「生きるって、こんなに素敵なことなんだ!」明日への希望が見つかります。
「キリスト者になる」ということは、「一つのものになる」ということだ。(本文より)
目次
1 現代社会でぶれずに生きるために
2 見えないものを見る力
3 ゆだねる勇気 受け入れる力
4 やさしい気持ちになりたくなる
5 自分らしく生きる
新書判並製 204頁 定価 本体740円+税
出版社: ドンボコス社
ISBN978-4-88626-581-4 C0216
ユダ 烙印された負の符号の心性史

いつどこで、誰が誰のことをユダと呼ぶのか?
裏切りの象徴はいかに生まれ、いかに描かれたのか?
古今東西の伝承や文献からユダの伝説を多角的に比較分析、
両義性に着目しながら、「負の符号」に託し託された心性を解読する刺激的論考。
[目次]
第一章 ユダの神学とキリスト教の成立
第二章 ユダの両義性
第三章 ヨーロッパにおけるユダ像のヴァリエーション
第四章 プロテスタントとユダ
第五章 ロシアのユダ
第六章 反ユダヤ主義とユダ
コラム
ユダと性 / ユダと美醜 / 「さまよえるユダヤ人」とユダ / ユダと音楽 / ネルヴァルのユダ / アベ・エガーのユダ / 諜報活動とユダ / ユダのDNA
著者のコメント
ユダとはイエス・キリストを銀貨30枚で売ったと言われる「裏切り者」のあのユダのことだ。なんだかんだ言っても「欧米キリスト教文化」の「先進国」主導である現代の国際社会において「裏切り」とは何を指すのか、裏切りと弾劾された後で名誉回復することはあるのか、などの「本音」を探りたいという意図が初めにあった。
調べていくうちに、「神」だとか「教会」だとかいう「蒙昧」から人間を「解放」して「近代」を築いたように見えるキリスト教文化圏の国において、「ユダ」だけは活きがよく不滅のようであることが分かった。社会がどんなに宗教離れして世俗的になっても、キリスト教や福音書のルーツがまるで「ユダ」を通して透けて見えるかのようだった。
それは興味深いことだったが、それにしても、ユダの物語に時代や文化を超えた大きな求心力があることはさらに不思議だった。
人が憧れ畏敬し模範とする聖人や賢人や偉人の話よりも、二千年前のローマ帝国の辺境で生きたユダという「大悪人ですらない男の物語」がどうしてこうも、より執拗に語り継がれ、反芻されるのだろうか。
そう考えているうちに分かってきたことがある。
ユダと言えば救世主イエス・キリストを売り渡した極悪人のようなイメージだが、実際は、大して悪いことをしていない。イエスをとらえに来た兵士らに「本人鑑定」をして見せただけで、イエスを鞭打ったり茨の冠をかぶせたり、十字架を背負わせたり、手足を十字架に釘で打ちつけたりしたのは全部別の者たちだ。ピラトによって恩赦の機会を与えられたのに興奮してイエスを殺せと言いたてた民衆の仲間ですらない。
そう、ユダは大した悪人ではない。
まあ、ほんの出来心でエデンの園の林檎をかじっただけで楽園を追われ、「神の似姿」から死に行く人間に格下げされて全人類に「原罪」を負わせたアダムの例もあるから、罪と罰のバランス感覚など所詮我々には分からない。けれどもユダを罰したのは神ではない。ユダは自分で後悔の念に苛まれた。そのユダを永遠に責めつづけるのは大した善人でもない人間たちだ。
その罪と罰、行為と罪悪感のアンバランスという落ち着きの悪さのせいで、実際多くの人がユダを「弁護」する側にも回ってきた。
ユダの裏切りなど全くの言いがかりでそんな事実はなかったのだという「歴史否定論者」みたいなものから「実はユダはイエスに頼まれた役どころを果たしただけなんだ」という「ユダとイエスの共謀説」みたいなもの、「いや、人間だもの、大した罪じゃないさ」という慰めや寛容、そしてひたすらの憐憫までいろいろなケースがある。
この本ではそれをいろいろ紹介したわけだが、実は、書き終わってからゆっくり見えてきたことがひとつある。
それは、ユダのこの「罪」が大したものではないからこそ、私たちに何かをもたらしているということだ。いや、「大したものではないにかかわらず、みなが罪悪感の対象にして語り伝えてしまう」ことそのものが意味することだ。
「悪の陳腐さ」というと、エルサレムの法廷でアイヒマンを見たハンナ・アーレントを思い出す。平凡な小役人的人物も時代の波や環境によって民族大虐殺のようなことをやってしまうという驚きだ。
ホロコーストはそれまでの西洋近代を牽引してきたというヨーロッパ人の自負の念を砕き、人間そのものまで信じられなくしてしまうほどの大事件だった。それがたとえ「悪の陳腐さ」を内包していたとしても、アイヒマンと比べて、公平に見てユダはやはり大したことをしていない。
ちょっとした出来心や怠惰や臆病や卑怯が人を「誤らせる」ことがある。運が悪いとそれが「神殺し」とまで呼ばれてしまうわけだが、ユダの程度の「過ち」はどんな人でも多少は覚えがある。
裏切りとまでいかなくても小さな背信の覚えは誰にでもある。自分を助けてくれる人、守ってくれる人、愛してくれる人に対して、ちょっとしたエゴイズムや気の迷いやよからぬ誘惑などの理由で、いやちょっとした思い込みや困難を避ける気持ち、溜まった疲れやストレスから嫉妬や羨望までさまざまな要因で、つい信頼や期待を裏切るようなことをしてしまう。善意の親に口答えしたり、自分の力不足や失念や失敗を知られたくなくて保身のために嘘をついたりすることから、パートナーや子供を疑って日記や携帯履歴をのぞいたりするようなことまで、「よからぬこと」をした時に私たちはそれを「よからぬこと」と認識してやましい気持ちを経験する。
けれども、だからこそ同時に、それを「責められたくない」「ゆるしてほしい」という気持ちを知ることができる。過ちを隠しおおせたり、なかったことにしたりするだけでは罪の意識は消えないからだ。
「小さな過ち」の体験によって私たちは「ゆるしてもらいたい」という思いを知るのだ。
アメリカで同時多発テロがあった翌年の初め、当時のローマ教皇ヨハネ=パウロ二世は、「平和には正義が必要で、正義にはゆるしが必要だ(正義なしの平和はなく、ゆるしなしの正義はない)」と言った。
平和を乱すテロ行為という絶対悪には正義の鉄槌を下さねばならない、とアメリカの大統領は息巻いていた。あの時点で「まずゆるしを」などと言える人はなかったろう。
けれどもアメリカが「悪者退治」を始めたそれからの世界がより公正なものになったわけでもより平和になったわけでもないことは誰でも知っている。
「ゆるし」の岩盤に打ち立てられた正義とそのまた上に打ち立てられた平和だけが本物なのだろうと納得できる所以だ。
怒りのうちに下した決断はすべて間違っている、とセネカは言った。なぜなら、怒っている時に人は自分が絶対に正しいと思っている。ところがだれかが「絶対に正しい」「完全に正しい」ということは不可能であるから、怒りのうちに下された裁きや決断は間違っている、と。
怒りの上に築かれた正義、その正義の上に築かれた平和は本当の平和ではないわけだ。もちろん反対勢力や弱者を排除したり抑圧したりすることで成り立つ「正義なしの平和」も見かけだけのものだ。
「ゆるしが正義や平和に先行する」ことに「納得」できるとしたら、それはまさに、誰でもが「ゆるしてもらいたい」という体験を共有しているからだろう。たいていの人は、自分を傷つけたり裏切ったりしたと思う相手を寛大に「ゆるす」ことはまれでも、「ゆるしてもらいたい」と思うこと自体は全身がむずむずするほど堆積していっているものだ。
「ゆるす」のがどんなに難しくても、「ゆるしてもらいたい」という心、あれやこれやの過ちを悔いる心を知っている限り、「ゆるす」側に立つことは決して不可能ではない。
ゆるすとは、自分と違う人を排除したり無視したり抹殺したりしないで「共に生きる」ということにつながる。意見が違う、外見が違う、文化が、伝統が、肌の色が、宗教が、国が、言語が違う人と共に生きることを拒否するところには、正義も平和も生まれない。
「自分と異なる者を排除する」というのはつまるところ、「私を誰よりも大切だと思ってくれない」他者を拒否することにつながる。裏切りや背信がゆるせない「悪」に見えるのは、「私の平和、私の幸福、私の安全」を脅かす他者を排除したいからだ。
でも、私たちはユダの葛藤、ユダの後悔、ユダの惨めさを見て、自分の中にも、あの人この人に「ゆるしてもらいたい」心があることを再認識する。
「ゆるし」が必要だというのは「ゆるされること」が必要だということと同義なのだ。
私たちの中のユダは、正義と平和の必要条件である「ゆるし」という難行をいつか可能にしてくれるかもしれない最も小さな芽のようなものだろうか。
人々が聖人伝を手離し、神や宗教から「卒業」した後も、なぜか「ユダ」の物語にこだわり嫌悪し続けてきたのは、ユダの持つ悪や背信や暗い部分に倒錯的に惹かれてきたからではない。
人が他者と共に生きるためには「ゆるし」が必要だ、とみなが直感的に知っていて、「ゆるし」の芽であるユダだけはどうしても捨てたくなかったのかもしれない。
神や偉人や聖人は、どうしても都合のいいようにいつしか「偶像化」されてしまう。
大悪人、極悪人も時として偶像化される。
私たちの中にもいる惨めな裏切り者のユダだけは、決して偶像化されることなく、良心とゆるしの感性を足元から灯す小さな光源であり続けるのだ。
20cm 213頁 2700円
出版社: 中央公論新社
978-4-12-004606-3(4-12-004606-0)
戦士ジャンヌ・ダルクの炎上と復活

小さな人生の閉塞感の中で心が折れそうな人、小さな人生で自分だけ無難に逃げ切るよりも終りのない大きな人生に参加して普遍性の航海に出発したい人、小さな運命から突きつけられる小さな人生の終戦勧告を無視して大きな運命の弾丸のとびかう戦場に駆って出たいと思う人たちの行く手を照らすために、ジャンヌ・ダルクを焼いた炎は消えることがない。(「あとがき」より)
聖俗を超えた少女のカリスマとその同時代性を明らかにする
ジャンヌ・ダルクといえば「フランスを救ったのに火あぶりになった少女」として日本でもよく知られている。もちろん史実としてはその通りだ。しかしジャンヌ個人のイメージはフランスでもある時代までは神話の域を出ることはなく、その実在性は希薄だった。例えば、ヴォルテールが書いた『オルレアンの処女』のジャンヌは、翼のはえたロバに乗って登場する。まさに神話のヒロインそのものだ。しかし、19世紀に公にされた「裁判記録」が事情を一変させる。文字として残されていたジャンヌの「生の」言葉が神話的キャラクターに血を通わせたのである。人々は彼女を生身の人間として驚愕のうちに再認識した。本書は、「ナショナリズム」「ジェンダー」「宗教と政治」という三つの視点を据え、中世における百年戦争の時代からEUの現代に至るまで、19歳で火刑台の炎と消えた少女が、聖と俗、左と右、男性と女性をめぐる戦いのなかで、ある時は各派のヴィジョンを映す鏡となり、ある時は国家統合のシンボルとなっていく経緯を、〈歴史批評〉とでも呼べる独自の手法で明らかにした快作である。そのインスピレーションの源は、若きカリスマに著者が発見したひとつの奇跡に違いない。その奇跡とは……?
[目次]
はじめに
序章 ジャンヌをめぐる記憶の更新と変容
生誕六〇〇年祭/オルレアンの熱狂/ルーアンの葛藤/暴力と追悼の風景
第一章 英仏の戦いとナショナリズムの萌芽
日本人が知らない英仏関係の実態/中世における英仏の確執/コーションという男/パテイの戦い/ジャンヌ・ダルクの異端審問/二つのフランス/百年戦争後の英仏関係/ドイツの台頭という脅威/欧州連合と独仏関係/ジャンヌ・ダルク症候群/アングロ・サクソンから見たジャンヌ/パリのジャンヌ・ダルク
第二章 ジェンダーの戦い
戦う女性たち/「小斧」のジャンヌ/戦いの報酬/一〇番目の女傑/奇跡のありか/男性として生きたカタリナ・デ・エラウソ/女装の男性の系譜/女装の神父/エオンの騎士/ヴォルテールの描いたジャンヌ・ダルク像/麗しきアニエス・ソレル/男装する「聖アマゾネス」/ジャンヌとアニエスの冒険/裸で戦うジャンヌ/ジャンヌの男装と集団幻想/「追い出された」ジャンヌ/二人の戦友/女預言者への期待/少女戦士のピュアな肉体/聖女たちの禁忌と自由/ル・マンの乙女/フランス王のカリスマ/大革命の女性戦士シャルロット・コルディ/讃えられない戦う女たち/犠牲の子羊から救国の殉教処女へ/一九世紀におけるフランス統合のシンボル/サラ・ベルナールとジェンダー/アンドロギュノス性の効果/ヨーロッパにおけるジェンダー観の系譜
第三章 宗教と政治の戦い
ジャンヌの聞いた「声」/「声」の謎と真の奇跡/政治プロパガンダとしてのジャンヌ/私を愛するものは続け/シャルル・マルテルの剣/異端審問の実態/ジャンヌの試練/聖なる女性が焼かれてしまった/戴冠と聖油の起源/癒しの業/シャルル七世の戴冠/王を待つ聖油/「民衆の聖女」の条件/聖女の取り込み合戦/さまざまな反応/女優に受肉した聖女/ブーランジスムとジャンヌ/ジャンヌを演じた聖テレーズ/さまざまな陰謀論──庶子説と生存説/「首謀者」ヨランド・ダンジュー/「英雄性」をめぐる物語/裁判記録の再発見とジャンヌの「肉声」/プロテスタント国のスタンス/権力によるジャンヌの取り込み/ドイツ占領下における解放のシンボル/ニコラ・ショーヴァン または蒙昧で勇敢な農民兵士
終章 お告げを聞いた二人の少女
ジャン・アヌイ『ひばり』/聖母マリアの場合/私たちが聞く二つの「声」
おわりに/あとがき
著者のコメント
『戦士ジャンヌ・ダルクの炎上と復活』
20世紀の終りに講談社現代新書で書きおろしたジャンヌ・ダルクの本には「聖女」をキーワードとしたので今回は「戦士」に注目してみました。
白水社の『ふらんす』に連載していた『ジャンヌ・ダルク異聞』で、自由に書かせていただいたものを骨子にしてまとめたものです。ナショナリズムと戦争、ジェンダーの問題、政治と宗教の関係、考えれば考えるほど今日的なテーマだと思いました。
今回は書けませんでしたが、ジャンヌにまつわる二人称の敬称と親称の使い分けもおもしろいと思ったことの一つです。
「もしお前に真の悔悛が現れるなら償いの秘蹟が授けられるだろう。」
1431年5月30日、ジャンヌ・ダルクが耳にした「戻り異端」の判決の、最後の部分です。ジャンヌ・ダルクは名もない平民の娘であったに関わらず、シノン城に王太子を訪ねた時以来、短い公的生活の中では一貫して二人称複数の「敬称」で呼ばれてきました。王や貴族たちと対等の立場で振る舞い、彼らからも対等に扱われてきたのです。
判決では二人称単数の「親称」が使われたのですが、それは当時の慣例であり、ジャンヌの戦友で大領主だったジル・ド・レが後に死刑判決を受けた時も同様に親称が使われています。決して、異端裁判だから、相手が19 歳の少女だからという「上から目線」の「お前」よばわりではありません。
ジャンヌに使われたもう一つの親称は、一人で神に祈る時に聞こえてきた「声」によるものです。「フランスを救え」などという途方もない使命を前にして逡巡する彼女をひと押ししたのは、「神の娘よ、行け、行け、行け」という声でした。
正確には「神の娘よ、行け、行け、行け、私はお前を助けよう、行け」
Fille De (fille de Dieu), va, va, va, je serai a ton aide, va. と記録されています。
ジャンヌは火刑台に送られる前に望みどおりマルタン・ラドヴニュという修道士に告解して免償を受け、聖体を拝受しました。戻り異端の判決を下したコーション司教自身が、その許可を与えたのです。
彼女を「神の娘よ」と呼んだ声は「親称」で語りかけ、異端であるとの宣告や償いの秘蹟の約束もまた「親称」によってなされたわけです。この世での出来事にはさまざまな礼儀やリスペクトの体系がありますが、神との関係の中ではそのような「上下」はないということでしょう。フランスでは今でも神に呼びかける祈りでは親称が使われます。
たとえば、日本語の「主の祈り」で「み国が…」「み名が…」「み心が...」「み旨が…」などと唱えられるところが、フランス語では全部「親称」なので、これを唱えさせられる子供たちや信者たちが抱く印象はだいぶ違ってきます。考えてみると、キリスト教は、人がありがたいものを偶像化して祀り上げるタイプの宗教とは違い、神が人となってあまつさえ抵抗せずに殺されたという点で神と人の関係や距離をラディカルに変えたものなのですから「親称」は本質をついているとも言えます。
だとしたら、勇敢な戦士で戦いのリーダーであったジャンヌ・ダルクも、「聖女」としては私たちのごく近いところにいて親称で呼び合える人なのかもしれません。
敬語抜きで「ねえ、ジャンヌ、私の冒険にもう少しつきあってね」と語りかけたい気分です。
四六判 上製 253頁 1995円 (本体価格1900円)
出版社: 白水社
ISBN978-4-560-08295-9
マリアのおはなし

マリアは、イエスのお母さんになれて、とても幸せでした。つらく苦しいことも、イエスといっしょに、愛する神様と人々のためにおささげした聖母マリアの物語。[小学高低学年から /総ルビ付]
マイテ・ロッシュ 絵と文 竹下節子 訳
著者のコメント
フランスの絵本ということで翻訳を頼まれたのですが、中身は福音書の文がほとんどそのまま使われているところが多いので困りました。フランスの子供たちには福音書の文もごく普通の日常語とかけ離れていないからです。マリア(マリー)という名前もどこにでもある名前ですし、神さまマリアさまだからといっても、いわゆる敬語が多用されるわけではありません。「愛する」とか「たたえる」とか「信じる」とか「お仕えする」とか「平和」とか「知恵」という言葉は、フランスの幼児なら普通の語彙でも日本の幼児になじみある語彙ではないので当初の「幼稚園児対象」というのを小学校低学年くらいのイメージに変えました。
できた絵本は、フランス判よりもすてきです。何がすてきかというと、表紙が少しふかふかでやわらかくやさしくつるつるで、絵柄とぴったりだからです。こんな肌触りのいい表紙でマリアのおはなしを読める子供たちっていいなあと思います。
257×227mm上製 39頁 定価1,050円
ISBN978-4-88626-546-3 C8716
カトリック・サプリ1 人生を活性化する25錠

真夏の神戸で男子高校生に交って炊き出しのボランティアに参加した「ボランティアで元気をもらう」、聖書のマルタとマリアのエピソードから没頭することの大切さを説く「マリアかマルタか」など、サプリメントのように少しずつ吸収できる粒よりな25のエッセイを収録。キリスト者として世の中を生きるための示唆があふれる一冊。
目次
はじめに
第一の処方箋 社会の中でキリスト教的に生きるために
あるイベント・クリエーターのはなし
ボランティアで元気をもらう
カリタスのはなし
パリのカトリック学校
ジーザス・フリークス
第二の処方箋 信仰と理性の狭間で迷子にならないために
聖骸布の人
信仰と科学
煙か風か
音楽と聖なるもの
兄弟愛と宇宙人
第三の処方箋 自分の生き方に自信がなくなったときに
原則の人
スピリチュアルとカトリック・ライフ
マリアかマルタか
偶像との戦い
不思議のルルド
第四の処方箋 祈れない夜のために
祈りのはなし
こんな祈りがあってもいい
「ゆるし」のテクニック
信仰と科学
母の死で考えたこと
第五の処方箋 愛といのちの関係を実感したいあなたに
父と子
母と子
ヨセフのクリスマス
父か母か
カトリックが好きなわけ
新書判並製 203頁 定価777円
出版社: ドンボコス社
ISBN978-4-88626-534-0 C0216
キリスト教の真実 ─ 西洋近代をもたらした宗教思想

ギリシャ思想とキリスト教の関係を検討し、近代ヨーロッパが覚醒する歴史を辿る。キリスト教という合せ鏡をとおして、現代世界の設計思想を読み解く探究の書。
キリスト教は、出現した当時のギリシャ世界において、既存の宗教の枠を超える「型やぶり」な思想であった。ユダヤ教から派生した「突然変異」ともいえるキリスト教が、ギリシャ思想の精髄を吸収しながら古代ローマ世界に浸透し、やがて近代ヨーロッパを覚醒させる。本書では、教義に内在する普遍主義の歴史的連続性を読み解き、修道院がその伝承を担った中世の世界をさぐる。近代主義者たちはキリスト教の歴史事実を意図的に否定するが、その歪曲がなぜ必要だったのかを考える。キリスト教という合わせ鏡をとおして、現代世界の底流にある設計思想を解明する探究の書。
目次
第1章 ヘレニズム世界に近代の種をまいたキリスト教
第2章 「暗黒の中世」の嘘
第3章 「政教分離」と「市民社会」の二つの型
第4章 自由と民主主義の二つの型
第5章 資本主義と合理主義の二つの型
第6章 非キリスト教国の民主主義
第7章 平和主義とキリスト教
著者のコメント
チュニジアやエジプトを発端に「アラブの春」と呼ばれるイスラム世界の民主化運動が始まってから、一年以上が経過した。しかし「民主的」選挙で選ばれた多数党は過去の独裁政権下で弾圧されていたイスラミスト政党で、これからはイスラムを基本理念にすると言い、それではイスラム革命をしたイランと同じではないか、と危惧する声もある。
ところが、民主主義下の政党が宗教理念を掲げること自体は、世界では別に珍しいことではない。日本のように、軍国主義の基盤となった国家神道から、敗戦によって、天皇が「神」から一転して「人」になり、無神論的な過激な政教分離の「民主主義」になった国のほうが特殊だ。国王を殺したフランス革命でさえ、ナポレオンの時代にはカトリック教会と和親条約を結んだし、神の国の建設を目指して植民者が開拓したアメリカのような国では大統領が盛んに「神」を口にしてはばからない。ドイツのメルケル首相は「キリスト教民主同盟」の党首だし、イギリスのエリザベス女王は英国国教会の首長である。
でも、誰もそれらの欧米諸国を「民主主義」でないとは言わない。彼らは、彼らの民主主義や人権思想を生んだ「西洋近代思想」の背後にキリスト教の神がいることを口にしなくても自覚しているからだ。だから、今のチュニジアのようにイスラムを軸にしようという新民主主義国家を、宗教色だけで批判することはできない。西洋は不寛容な戦いを何世紀も繰り返してきてようやく彼らの宗教から抽出した普遍的な価値(自由、平等、友愛)を政治理念に掲げた。それは多様化する世界でのサバイバルと共存の知恵として世界中で広く認められつつある。
といっても、政教分離のさじ加減というのはどこの「民主主義国」でも独自の文化や歴史やメンタリティに応じて、かなり違っている。イスラム国でもアラブ系ではないトルコやインドネシアなどでは、けっこうフォークロリックな政教分離が見られる。中には、形ばかりの「勘違い」もある。
また、近代世界を牽引した本家のキリスト教圏欧米でも、一六世紀の宗教革命や一八世紀の市民革命の時点においてどんな教会が政治的にどのような勢力を持っていたかによって、その後の政教分離の建前と実際や、民主主義の落とし所は微妙に違ってくる。ところが「欧米」の内輪同士では、それらの差異を混同することなく、自分たちがどういう政教分離のどういう民主主義で、相手のそれはどういうものなのかを互いによく心得ている。同じローマ・カトリックの根っこから分かれてあれほど激しく殺し合いを続けて血を流してきて、やっと棲み分けの智恵をつけた文化圏なのだから、当然なのかもしれない。
彼らが狡猾なのは、それだけ異質なくせに、非キリスト教世界や非欧米世界に向けては、まるで申し合わせたように同じ口調で「民主主義」や「自由平等」などを唱えるところだ。これでは、「圏外」の人にはなかなか実態を見抜けないし、「使い分け」のリテラシーも身につかない。特に、たとえばアングロ・サクソンの情報源に頼っていれば、無神論系やラテン系の民主主義のニュアンスをつかむことは難しいし、「欧米」内談合の機微をうかがうのも楽ではない。
もちろん、民主主義の理念などに興味を示すふりをする必要もないほど人口的にも経済的にも軍事的にも勢いがあって上り坂にある大国であれば、機微も必要なく、リアルポリティクス一辺倒で押していけるのだろう。でも、日本のように、「欧米」先進国と同じように疲弊して低成長なのに、欧米の「老獪民主主義」パワーの仲間になれるパスワードを持っていなければ、国際社会の中で「空気を読めないヒト」とみなされてしまう。欧米民主主義を解読するキイとは、普遍主義の戦略上、彼らが敢えて口にしないキリスト教のルーツである。『キリスト教の真実』が、日本が国際社会をサバイバルするヒントになることを願っている。
シリーズ:ちくま新書 ページ数:288 定価:924円
出版社: 筑摩書房
ISBN:978-4-480-06659-6
JANコード:9784480066596
聖者の宇宙

古代、中世から現在に至るまで、カトリックが認定した様々な聖者の逸話を辿りながら、誕生の過程とシステムを分析する。神と人の間をとり結ぶ聖者 が各々に果たす役割を論じつつ、民衆の想像力や祈りの意味を問い質す「聖者論」の決定版。
著者のコメント
1998年に青土社から発行された単行本に加筆修正を加えた文庫版です。この10余年の間に、21 世紀が始まり、ローマ教皇が代替わりし、イスラム過激派がアメリカを直接攻撃したことで宗教と無関係ではいられない戦争がアフガニスタンやイラクで展開されました。「聖者の宇宙」をかかえるキリスト教的に見ても、緊張の絶えない時代に突入しているわけです。
カトリックにおける聖人崇敬はプロテスタントの多くからは否定されてきたものなのですが、偉い神さまや尊顔を拝することのできない神さまよりも、そんな神さまを信じて人間としての生を全うした「人間仲間」の聖人さまにすがってみたい、という気もちはいつの世にも人情なようで、いろいろな聖人たちは21世紀でも大いに頼られています。
カトリック教会の聖人とはこの世での生はすでに終えた人々ですし、その認定も、死後かなりの間を経たものとされていますから、認定されたからと言って直接の利害が生まれるわけでもありません。もちろん認定された時代の政治の思惑やら民衆感情と無縁でないものもありますが、何しろ定員がないし任期もないので、増えるばかり、「政治利用」されたり個人のエゴや名誉のために利用されることはありません。
今回の加筆では、p166から、日本が関係した「奇跡」に触れています。そこでは日本はいい役どころではありませんが、「文庫本のためのあとがき」で書きましたように、日本では2008年に、江戸時代初期に幕府の迫害で殉教した日本人キリシタンの列福(聖人認定の前段階)が、日本人主導で実現しました。
これはなかなかすてきなことだと思っています。
なぜなら、中国やベトナムでは、ヴァティカン主導の殉教者の列福があると、抗議行動が起こることを考えてしまうからです。自国の殉教者とは、当時の政府の禁止に反抗した犯罪人であり、「宣教師の手先」の国賊だと見なされるので、殉教者の美化はあり得ません。ところが日本は、江戸時代の政府の「反逆者」であった殉教者を自分たちで聖人にしようとしました。それに対する抗議行動はないし、いや、実際、江戸時代の当時でさえ、信仰を捨てずに従容として死を受け入れたキリシタンへの畏敬やリスペクトを示した領主や領民も少なくなかったのです。
中国の民主運動家の劉暁波さんが2010年のノーベル平和賞を受けたことに対して、中国政府が情報統制などして遺憾の意を示したことは記憶に新しいですが、そのニュースを聞いた時に、殉教者の列福のことを思い出してしまいました。
それにくらべて、日本人の宗教的感世の中の、「八百万(やおよろず)の神」的な何でも共存のちょっとアバウトでシンクレティックな部分は、キリシタン迫害の凄惨な歴史を超えて、健康的に機能しているなと思います。
実際のところ、突き詰めて考えれば、聖人システムに関する「聖徒の交わり」と言われている教義は、死者も生者もすべての人が神の愛の中で分ちあい交信し合うという考え方なので、生と死とか善悪とかも超えてしまう「異なるみんなが一つの体の中で支え合いながら生きる」というイメージです。聖者の宇宙は、誰でも参入できる開かれた宇宙というわけです。複雑なようで実は懐の深い世界です。
どうぞのぞいてみてください。
キリスト教国では子供の名をつける時の参考に聖人本はたくさんありますが、日本では全貌をコンパクトにまとめた一般向きの本は少ないので役に立つと思います。
文庫: 377ページ
出版社: 中央公論新社
ISBN-10: 4122054036
ISBN-13: 978-4122054035
陰謀論にダマされるな!

陰謀論を仕分けしよう
情報が飽和するサイバー空間において、陰謀論と終末論は、個人の恐怖や不安を養分とするかのように際限なく肥大する。
フリーメイスン、イルミナティ、ユダヤ人、ヴァティカン、アメリカ政府など、陰謀論に繰り返して登場する面々は、いろいろな組み合わせで使いまわされる。時に、これらの役者同士が、互いに陰謀論を投げかけ合う。やがて、そこに擬似科学を駆使した陰謀論が入り込む。事件の解説型陰謀論から、メガ陰謀論、終末予言型陰謀論へと進化する。
無数の陰謀論と終末論を前にして、伝統的な知性による取捨選択は容易ではない。しかし、それでもなお、仕分けなければならない。「世界は悪意に支配されている」という考えと、人はいかに付き合うべきなのか。
著者のコメント
これは、私の中では前作の『無神論』とセットになっています。陰謀論は無神論のヴァリエーションの一つだと思うからです。またこの本は『カルトか宗教か』(文春新書)で取り上げた健康カルトなどの批判の延長にもあります。私たちが健康や将来に悲観する時にしのびよる脅しと救いがセットになっている言説について大いに考えさせられるからです。この本の終わりにはフランス・バロック音楽が出てきます。陰謀論との関係はなんでしょう?
ベスト新書 283 KKベストセラーズ ベスト新書
無神論—二千年の混沌と相克を超えて

無神論を語ることは神を語ることだ。古代ギリシャからポストモダンまで、世界史の原動力となった「負の思想」の系譜を辿りながら、その変容と対立を見つめ 直し、人間の存在や生き方について新たな可能性を模索した画期的な論考。
(あとがきより)
著者のコメント
日本で生まれ育った間、生活の場においてキリスト教的なものとほとんど縁のなかった私は、フランスに住むようになってから、キリスト教的なさまざまなフォークロアに出会って非常に興味をそそられた。日本にとって近代のお手本のようなヨーロッパには、前近代的で土俗的、いや、前キリスト教的な異教の香りさえ放つスポットやシステムがあちらこちらに残っていたからだ。
考えてみれば、日本の近代化は「和魂洋才」を掲げて、宗教との対立を避けてきたが、ヨーロッパにとっての近代化の道は、キリスト教を否定せざるを得ない身を切るような「無魂洋才」の葛藤だった。近代ヨーロッパ人たちはキリスト教普遍主義を世俗化していき、苦労して神なき「洋魂」を練り上げたものの、神殿から追われた神や神々たちは、姿を変えたり先祖返りしたりしながら、そこかしこに取り残されたままなのだ。近代は、自由な個人を神から解放するのには成功したが、神々を人間たちの思惑から解放することには手をつけなかった。
近代化を生きのびた神々の残滓も、進化してきたキリスト教の姿も、老舗宗教が提供する知恵や風景も、私には新鮮で、これまでに『パリのマリア』『聖女伝』『ローマ法王』『バロックの聖女』『知の教科書キリスト教』『聖母マリア』『弱い父ヨセフ』『聖女の条件』など、キリスト教に関するいろいろな本を書いてきた。そのいずれも、ごく普通の日本人読者を想定したもので、知的好奇心による反応はあっても、信仰の言葉による違和感を表明されたことはほとんどないし、信仰についての私のスタンスを問い詰められたこともない。ところが、フランスでは違った。私が聖人伝だの聖遺物だの奇跡譚だのを熱心に調べていることを知ったフランス人は、半分くらいはそれを面白がり蘊蓄を傾けてくれるが、後の半分はショックを受けて露骨に忌避反応を示すのだ。その典型的なタイプは、地方のイエズス会系の中等教育を受けたブルジョワ家庭のエリートで、バカロレアの後で哲学を専攻してリセの哲学教師になっているような人である。
そのような人にとっては、私の調べているテーマは忘れたい過去、捨てた蒙昧であり、ほぼタブーを形成しているのだった。彼らにとっては、知的な人間がそんなことに興味をもてるのはまさに不可能なことであるらしかった。日本でも有名なエリート校であるエコール・ノルマルは師範学校で、フランス革命以来の世俗共和国主義の牙城である公教育の理想を受け継ぐ。そしてそこには、革命以来の「インテリ=左翼=無神論者」という等式が存在していたのだ。その無神論とは、無関心ではなくイデオロギーに近いものですらある。多くのインテリ左翼にとっての無神論のこだわりは、見えない宗教といっていいほどで、時として原理主義的で闘争的だ。代々のカトリック家庭の人の多くがキリスト教を冠婚葬祭に関わる地域宗教としてのんびり生きているのとは対照的である。
いったんそのことに気づけば、ヨーロッパ近現代の思想や歴史の意味することや、そういう葛藤を経ずに神の国を建国したアメリカとの違いが別の光のもとに現れる。キリスト教自体も、キリスト教無神論という合わせ鏡を通してはじめてはっきりと立体的に見えてくることがたくさんあるのだ。
現代世界においては、経済の南北格差と宗教原理主義の問題や独裁国における信教の自由の問題が切実なものになっている。日本やフランスには、近代化の後遺症があって、それらの問題には必ずしもうまく対応できない。その後遺症とは、日本の場合は「宗教帰属心の風化」で、フランスの場合は「無神論者たちの長く熾烈な戦いの戦禍」と、まったく対照的な症状を呈するものだ。その状況を把握しない限り、フランスについてもキリスト教についても現代のグローバル世界の危機についても、日本人による認識から大切な部分が落ちることになるだろう。
この本は、これまでに紹介してきたキリスト教的心性を反対側から眺める合わせ鏡を提供するために企画された。無神論という視座から思想史を眺め返すことは刺激的で、奥に入り込むことが多く、作業はなかなか進まなかった。これはひとまず最初の問いかけである。
単行本: 285ページ
出版社: 中央公論新社 (2010/05)
ISBN-10: 4120041204
自由人イエス—もう一つのキリスト論 (単行本)
ク リスチャン デュコック著、
竹 下 節子訳
 本書は、イエスが同時代人たちからどう見なされていたのか、イエス自身は自分をどう見ていたのか、彼の断罪の意味は何だったのか、そして、どのようにイエ スは「赦し」によって憎悪を克服したのかを明かし、イエス・キリストにおける神の啓示まで、歴史学的に要約しつつ、段階を追って解き明かしていく。 本書は、イエスが同時代人たちからどう見なされていたのか、イエス自身は自分をどう見ていたのか、彼の断罪の意味は何だったのか、そして、どのようにイエ スは「赦し」によって憎悪を克服したのかを明かし、イエス・キリストにおける神の啓示まで、歴史学的に要約しつつ、段階を追って解き明かしていく。
ナザレ のイエスが、その生と死と復活によって今も私たちを自由に向かって導いてくれることを説得力をもって明示する、躍動的なキリスト論。
著者略歴
ク リスチャン デュコック
Christian Duquoc
ドミニコ会司祭。リヨン・カトリック大学の神学教授、カトリック雑誌『Lumi`ere et Vie』の編集長を務める。著書多数。1926‐2008年
竹下節子による解説より
(・・・・)
聖書におけるイエス・キリストについて語る時のアプローチの仕方はいろいろある。
書いてある字面を字義通りに解釈する直解主義は、蒙昧的な原理主義に陥ったり、逆に、その蒙昧ぶりを過度に忌避する宗教拒否や無神論をも生むので、ここでは問題外だ。
その他には、聖書の各種の訳、写本の比較、語彙や技法や様式などを分析して編集や伝承の実態を明らかにする文献の歴史学的解釈が存在する。それに対して、それは所詮精密科学を模した疑似科学に過ぎないとして、解釈者の文化的思想的文脈に基づいてテキストと主観的に対決する哲学的解釈もある。個人的な思索がやがて普遍へと結びつくという考えだ。
この本は、神学的迷路に迷い込むことなく、イエスの復活の意味、彼に冠されたさまざまな呼称の意味について、歴史学的に要約してたどってくれる。いろいろな解釈者の試行錯誤を丁寧に紹介した上で、主観的解釈ではない、キリスト教成立の根本にあった劇的転回に迫る。そこには哲学的解釈における解釈者の主体への沈潜という過程はなく、最初から、キリスト教に内在する解放のムーブメントを視野に入れ、その中でのみまっすぐに進んでいく。その様子はまさに、聖霊に吹かれながら私たちを巻き込んでいく爽快なものだ。
このようにして、文献の編集や様式にまつわる困難をひとつずつ丁寧に整理し、最後に残ったものこそ、人間イエスがキリストとなって神と人とを同時に解放した決定的な動因である「自由」なのである。
考えてみると、「自由」という言葉は、日本でも普通に使われているけれど、残念ながら、翻訳語の概念だ。やまと言葉的には、「自らに由る」のは、心のまま、思いのまま、気まま、わがまま、という概念につながることもある。
この本がイエスを「自由人」と形容する時、それが、他者の思惑を気にせず「自分ワールド」に住む勝手な人間を意味するのでないことはもちろんだ。確かに、史実のイエスは、当時のファリサイ人や祭司たちが律法のコメンテーターとしてふるまい語ったのに対して、クリエーターとして、権威をもってふるまったことで人々を惹きつけたと著者は指摘する。イエスの屈託のなさや、本音と建前の食い違いのない自然な言行一致、社会的偏見にとらわれないその自由人ぶりが周りの人にとって非常に魅力的だったわけだ。
しかし、人々はイエスの自由を、「抑圧された自分たち」を解放してくれるという期待に閉じ込めようとしてしまった。ところが、イエスの自由とは、すべての人と神とを同時に解放していくような自由だったのである。
その「自由」とは、冷戦後の新自由主義経済が、あらゆるレトリックを駆使して弱肉強食のバランスを保全するために掲げた「自由」でももちろんない。イエスが命をかけた「自由」とは、他者を無視したり、他者を抑圧するような、あらゆる種類の「見せかけの自由」の構造を揺るがす力動を生む最初の一押しである。人間の悪の連鎖が生む悲惨のただ中に身を置いて神に呼びかけることで解放の連鎖を生んでいく力動を、イエスはその生と死と復活をかけて始めたわけで、その力動の中でイエスは永遠に生きているし、その道においてのみ、私たちも生き続けることができると著者は言っているのだ。
キリスト教が切り開いた革命的な「歴史性」はここにある。個人がたとえ自らの死で購うことになっても、常に自分と他者の自由のために戦うことによって、自由をつなぎ、歴史を切り開いていく期待を、イエスの生と死と復活がもたらしたのである。
今の世界でも、悪と暴力の連鎖は次から次へと生まれ、すべてが死へと向かっている。そんな中で、私たちは、太古の日本だとか、自然宗教の悠久性とか、ストア派風のコスモスの完璧な秩序とか、永遠回帰の思想とか、解脱や悟りに見られる泰然自若、幽玄、エントロピーの増大した弥勒の無の世界のようなものに憧れ、キリスト教的な進歩主義の線的歴史観や自然管理を批判てしている場合だろうか。
抽象的な永遠とか絶対とかを持ち出して現状維持、秩序維持する文化には、必ず、その維持を支える犠牲のシステムもあり、秩序維持のために一部の人々の自由を奪う構造もある。祖霊を祀るとか、氏神を祀るとか、自然神を敬うとかいうレトリックの影には、共同体における権力システムの継承のために個人の死を封じ込めるという、死の取り込みがあったことを忘れてはならない。
「無宗教的」エコロジーブームやスピリチュアルブームの中でリラクゼーションして宗教間対話や異文化理解を怠っていると、結果的には、より大きい暴力装置の保全に加担することになるかもしれない。
私たちは他者を常に死から解放していくような形で自由を行使しなくてはならない。そうすれば、自分の死も、そのような自由の行使として、歴史を次につなげていく、生きたものとなることだろう。
著者のコメント
この本について、難しくて中途で挫折したという話も耳にしました。確かに最初は難しいのですが、最後まで来ると、おおおっというくらいに気分よく解放されます。ある意味、このくらい、明快で本質的なことをちゃんと言って、神学という業界で聞いてもらうには、それだけの緻密な論の立て方が必要とされることです。私はここで言われているメッセージを、キリスト教とかイエスとか聖書とかいう言葉を全く使わないでリライトするプランを温めています。タイトルは、「自由他在の思想」です。
単行本: 237ページ
出版社: ドンボスコ社 (2009/12)
ISBN-10: 4886264956
弱い父 ヨセフ

キリスト教における父権と父性
父は弱い。だが父は強い。父の「原型」から21世紀の父親像を考える。
受け入れ、養う。それが父親の役割だ。望まずしてイエス・キリストの父となった聖ヨセフ。聖書にはほとんど言及のなかった1人の「父」がすべての「父」のモデルになったのはなぜか。ヨセフ像の変遷をたどりながら、現代に必要とされている真の父の「ありかた」を考える。
目次
序章 可能性のヨセフ
第1章 ヨセフの生涯
第2章 観想のヨセフ——聖フランチェスコの馬小屋
第3章 政治のヨセフ
第4章 ヨセフが父になったわけ
第5章 不思議のヨセフ
第6章 ヨセフの21世紀
終章 「強い父」と聖ヨセフ
著者のコメント
前に同じ選書で『聖母マリア』を出したので、だんなさんのヨセフを並べたくて企画しました。ヨセフは地味ですが、なかなかパワーのあるキャラです。それなのになぜタイトルが『弱い父』かというと、それが編集者の希望だったからです。
いやしくもイエス・キリストの養父を「弱い父」と言ってしまうのはちょっと迷ったんですが、良く考えると、このヨセフを家長とする聖家族のメンバーの名を唱える時、昔から、「イエス・マリア・ヨセフ」と唱えるんですね。危機に瀕した時に「お助けを!」という感じで「イエス・マリア・ヨセフ」です。必死に働いて聖母子を守ったヨセフはいつも最後です。まあ、イエスは神の子、マリアは人間だけど、お母さんのアンナの体に宿った時から原罪を免れているそうですから、生まれつきの聖女で、この順番以外は考えられないでしょう。
ふと、日本の家庭内ヒエラルキーというか、家で大切にされている順番というかを示す表現を思い出しました。
「子供、母、犬、猫、父、金魚」というやつです。これを聞いたらたいていのお父さんは、「ああ、金魚の下でなくてよかった」とほっとするとかいうやつです。昔は「地震、雷、火事、親父」と、最下位ながら「怖い」存在だったはずなんですが・・・今じゃせいぜい「ちょいワル親父」とか、「ちょい」ですよ。
いまどき「父権」なんて持ち出すと「それなに?」って言われそうだし、妻からどんなにモラル・ハラスメントを受けても、手を上げればDVで、妻から殺されることすらあるようです。中高年男性の自殺はすごい数です。いったん「父権」を手放すとここまでくるのでしょうか。
で、「イエス、マリア、ヨセフ」という最後尾の立ち位置だったヨセフは、決して今の日本の多くのお父さんたちにとって遠い存在じゃないわけです。だから、弱い父ヨセフが実は最強の父でもあることの秘密を是非さぐってほしいと思ってこの本を書きました。父権や父性というジェンダー・イメージも考え直してみようと思いました。そう、誰でもヨセフになれるし、ヨセフ的幸福に照らされることもできるのです。
一般書で聖ヨセフについての本は日本では少ないかと思うので、キリスト教文化圏における聖ヨセフの姿をいろいろな面からとらえました。いろんな読み方をしてくだされば嬉しいです。この著作紹介のコーナーに、これまでの本の正誤表も載せていく予定なので、このヨセフの本についても気がつくことがあればどうか感想欄にお寄せください。どんなに注意していても単純ミスはもちろん、思い違いや勘違いや間違いが残ることがあり、ご指摘によって直せるところは直そうと思っています。
では、弱い父、聖ヨセフをどうぞよろしく。
(2007/8/15)
講談社選書メチエ(2007/8) 1575円
レオナルド・ダ・ヴィンチ 伝説の虚実

創られた物語と西洋思想の系譜万能の天才、魔術師、同性愛者、両性具有者、秘密結社の首領… ルネサンス以降、様々な妄想により紡がれたレオナルド・ダ・ヴィンチをめぐる伝説の背景と系譜を西洋思想の地下水脈から検証する。
『ダ・ヴィンチ・コード』の関連書はたくさん出ていますが、個々の領分についてコメントをつけたものばかりです。唯一、大きな世界観にたって『ダ・ヴィンチ』をめぐる伝説について分析した作品です。
ダ・ヴィンチをめぐる伝説の生成背景と系譜を検証
「ひとりの芸術家が、今日に至るまで、なぜ様々な物語の主人公にされてしまったのか」に着目、ルネサンス以降、どのような形で生まれ、どのように変わっていったかを検証する。ダ・ヴィンチ本の多くが謎解きや暗号解読に振り回された雑多な内容ばかりのなかにあって、ダ・ヴィンチが生きた時代とキャラクターが西洋思想の大きな流れに取り込まれやすかったかを解読する画期的な論考です。
ルネサンス以降に紡がれた様々な知識人の妄想
ダ・ヴィンチについて最初の評伝を書いたヴァザーリの創作にはじまり、フロイトの誤読、憂愁の世界に妄想したボードレール、ヴァレリーの誇大評価、世紀末の徒花ペラダン、さらに『レンヌ・ル・シャトーの謎』、『ダ・ヴィンチ・コード』などアングロサクソンによる異端・陰謀史観にみられる類似性を指摘し、数世紀にわたってダ・ヴィンチの物語がいかに増幅されていたかを多くの図版と資料により解説。
中央公論新社 (2006/05) ¥1,900+税
聖骸布の仔
ディディエ・ヴァン・コヴラルト著、竹下節子訳

僕はキリストのクローンなのか?
次々と起こる不思議は奇蹟なのか?
2026年、アメリカ政府はイエスのクローン計画を再始動、聖骸布の血痕から創られたという若者を発見した!
聖なる血脈を受けついだ彼の運命は?様々な陰謀が渦巻き、予期せぬ結末を迎える…。
ディディエ・ヴァン・コブラルト
DIDIER VAN CAUWELART
1960年、フランス・ニース生まれ。82年に『20歳と少し』でデビュー。「抑制された文体」と絶賛され、デル・デュカ賞受賞。84年に『愛の魚』でロジェ・ニミエ賞、87年に『幽霊のバカンス』でグーテンベルク賞、94年に『片道切符』でゴンクール賞。97年にミシェル・ルグランと共に作った『壁抜け男』(マルセル・エメ原作)はその年のモリエール賞(ミュージカル部門)を受賞。映画やテレビのシナリオからコミックの原作まで幅広い活躍をしている。2001年にはメキシコシティに実在するカトリックの聖遺物であるグラダルーペの聖母像をテーマに『御出現』を発表した。
中央公論新社 (2006/04) ¥2,200+税
アメリカに「NO」といえる国
 日本では「欧米」とひとくくりにされるキリスト教文化圏ですが、本当のところは「欧」と「米英・アングロサクソン」の真っ二つに分かれています。その違いを解説し、アメリカ〈グローバリズム〉に「NO」と言った唯一の国〜フランスの政治姿勢をユニヴァーサリズムの視点から分析します。 日本では「欧米」とひとくくりにされるキリスト教文化圏ですが、本当のところは「欧」と「米英・アングロサクソン」の真っ二つに分かれています。その違いを解説し、アメリカ〈グローバリズム〉に「NO」と言った唯一の国〜フランスの政治姿勢をユニヴァーサリズムの視点から分析します。
文春新書(2006/2/20)\777
聖女の条件—万能の聖母マリアと不可能の聖女リタ

ジャンヌ・ダルクからマザー・テレサまで様々な聖女の数奇な生涯と奇蹟の謎を探る。
なぜ無数の聖女が必要とされるのか?気鋭の比較文化史家・宗教研究家が、ローマ・カトリックが受け入れてきたフォークロワ的側面を照射しつつ、様々な聖女を、社会・文化的背景や心理、宗教などの観点から多角的に分析、人々の癒しの構造を探る「聖女伝」の決定版。
中央公論新社 (2004/11) ¥2,310
大人のためのスピリチュアル「超」入門

お告げが聞こえた?御出現に立ち合った?古今東西の不思議現象から五感の官能と敬虔を見極め、水、火、夢、オーラ、占いなどから 聖なる力を拝領する……
「あっちの世界」と上手につきあうための神秘主義の実践は、現実の生産生活にどっぷりと漬かっている普通の大人にも可能だ。日常を離れて、知覚不可能な「あっちの世界」を垣間見たり、感じたり、メッセージを受けたりしながら、結果的に日常を充実させその後の生き方を決定するものだ。大人の神秘主義とは、特定の教義や教祖に取り込まれることなく、ある程度知的に処理して、危機管理をしながら楽しめ、しかも魂の深いところを癒し養ってくれるようなものでありたい。本書では、知覚不可能領域とのコミュニケートの可能性に着目して、ミスティカル・サーフを試みよう。神秘主義を構成しているシンボリックな言語がわかるようになったら、後は自己流にアレンジできる。そうしたら、「マイ神秘主義」の始まりだ。
中央公論新社 (2005/04) ¥1,365
バロック音楽はなぜ癒すのか—現代によみがえる心身音楽

バロック音楽はなぜ「癒す」のか。その謎を、当時のヨーロッパで主流だった身体論にアプローチすることで問題を掘り下げ、解き明かす。
人間は心身を備えた存在で、その「心身まるごと」を追求したのがバロック音楽である。近年、バロック音楽が「癒しの音楽」として復活したのは、それがすぐれて心身的な音楽だからである。本書はバロック音楽の実践を通して心身の良好感をとりもどすための案内であり、著者の体験を通した比較文化的視点から語られる新しい心身論である。
目次より
「気の動き」に注目するバロック/高齢者と障害児を教える/東洋的身体観を持つフランス・バロックとその変容/ピアノのタッチと共感覚/音楽の色彩感と科学主義/近代産業としての音楽と舞踊/クラシック・バレエの体/音楽のキネジテラピー(整体術)/自己暗示とムドラ/音楽療法としてのコンサート/出雲の阿国はバロック音楽を聴いたか/プロテイン・ミュージックの不思議/アンサンブルと神秘体験/太極拳とバロック・バレエ 他
音楽之友社 (2003/10) ¥1,680
ローマ法王〜二千年二六五代の系譜

コンクラーベとは? 護衛兵はスイス人? 女法王がいた? ベネディクトとは欧州の守護聖人?
十億八千万にものぼる世界のカトリック信者のネットワークを駆使した最先端のヴァーチャル国家ヴァティカン。その頂点に立つローマ法王とは如何なるものなのか? 二千年にわたってヨーロッパの文化や精神の核として歴然と存在し続けたこの超国家的・超宗教的な怪人の姿を過去・現在・未来の重層する歴史の中に探る。
中公文庫(2005/06)¥781+税
パリのマリア—ヨーロッパは奇跡を愛する
筑摩書房 (1994/03)
聖母マリア—「異端」から「女王」へ

講談社 (1998/08)
ヨーロッパの死者の書
筑摩書房 (1995/08) ¥693
バロックの聖女—聖性と魔性のゆらぎ

工作舎 (1996/08) ¥2,520
不思議の国サウジアラビア—パラドクス・パラダイス

文春新書 (2001/07) ¥714
ノストラダムスの生涯
朝日新聞社 (1998/01) ¥1,890
ジャンヌ・ダルク 超異端の聖女

講談社新書 (1997/01) ¥735
知の教科書 キリスト教

講談社選書メチエ (2002/09) ¥1,680
からくり人形の夢—人間・機械・近代ヨーロッパ

岩波書店 (2001/02) ¥2,625
聖女伝—自己を癒す力

筑摩書房 (1995/09) ¥2,854
カルトか宗教か

文春新書 (1999/11) ¥693
さよならノストラダムス

文芸春秋 (1999/06) ¥1,600
奇跡の泉ルルドへ

気球の本 NTT出版 (1996/01) ¥1,325
テロリズムの彼方へ、我らを導くものは何か

文春ネスコ (2001/12) ¥1,365
聖者の宇宙

青土社 (1998/07) ¥2,730
ノストラダムスとルネサンス
分担執筆の著作でこの中の「カバラとノストラダムス」を書いています。
岩波書店 (2000/02) ¥3,045
グノーシス 陰の精神史
分担執筆の著作でこの中の「フリーメイスンとグノーシス主義」を書いています。
岩波書店 (2000/02) ¥7,140
翻訳:聖カタリナ・ラブレ
A. キュレリオーギュスタ, M.G. ルー著、 竹下 節子 翻訳
ドン・ボスコ社 (2001/04) ¥945
翻訳:聖ヴィセンシオ・ア・パウロ
A. キュレリオーギュスタ, C. エティヴァン 著、竹下 節子 翻訳
ドン・ボスコ社 (2001/04) ¥945
翻訳:聖ルイーズ・ド・マリヤック
シスター・ジュヌビエーヴ・ルー 著 竹下 節子 翻訳
ドン・ボスコ社 (2001/04) ¥945

|






 2021年4月30日、ベネズエラで「貧者の医師」として慕われたホセ・グレゴリオ・エルナンデスJosé Gregorio Hernándezがローマ教会から福者の列に加えられた。
2021年4月30日、ベネズエラで「貧者の医師」として慕われたホセ・グレゴリオ・エルナンデスJosé Gregorio Hernándezがローマ教会から福者の列に加えられた。

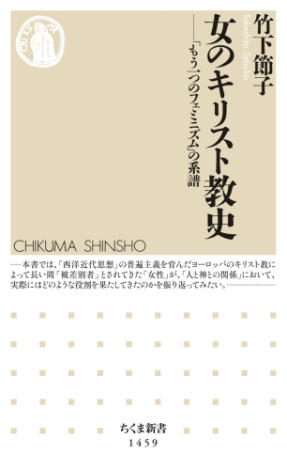

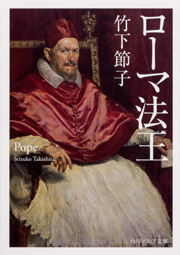


















 本書は、イエスが同時代人たちからどう見なされていたのか、イエス自身は自分をどう見ていたのか、彼の断罪の意味は何だったのか、そして、どのようにイエ スは「赦し」によって憎悪を克服したのかを明かし、イエス・キリストにおける神の啓示まで、歴史学的に要約しつつ、段階を追って解き明かしていく。
本書は、イエスが同時代人たちからどう見なされていたのか、イエス自身は自分をどう見ていたのか、彼の断罪の意味は何だったのか、そして、どのようにイエ スは「赦し」によって憎悪を克服したのかを明かし、イエス・キリストにおける神の啓示まで、歴史学的に要約しつつ、段階を追って解き明かしていく。


 日本では「欧米」とひとくくりにされるキリスト教文化圏ですが、本当のところは「欧」と「米英・アングロサクソン」の真っ二つに分かれています。その違いを解説し、アメリカ〈グローバリズム〉に「NO」と言った唯一の国〜フランスの政治姿勢をユニヴァーサリズムの視点から分析します。
日本では「欧米」とひとくくりにされるキリスト教文化圏ですが、本当のところは「欧」と「米英・アングロサクソン」の真っ二つに分かれています。その違いを解説し、アメリカ〈グローバリズム〉に「NO」と言った唯一の国〜フランスの政治姿勢をユニヴァーサリズムの視点から分析します。















