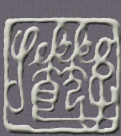 |
おたより |
考えるタネ 1 考えるタネ 2 美術室 1 美術室 2 バロック音楽室 1 バロック音楽室 2 ジェンダーの部屋 1 ジェンダーの部屋 2 ヒルデガルドの部屋 カトリック・ウォッチング 1 カトリック・ウォッチング 2 ネコ・カフェ できるだけ、と、もう少し おたより
|
||||
竹下節子公式サイト Home Sekkoの本 Errata L'art de croire Schubertiade Trio Nitetis トリオ・ニテティス たかが、かた (肩) Forum + 自由コメント Forum 1 アーカイヴ Forum 2 アーカイヴ Forum 3 アーカイヴ |
読者の感想竹下節子の著作をお読みいただいて寄せられた感想です。ご感想がありましたら、引き続き Forum のおしゃべりにご参加ください。name:TN 様 『アメリカに「NO」と言える国』を読ませて頂きました。最近はブッシュ大統領や小泉首相を批判的にとらえる本も少しずつ出版されるようになってきましたが、一時はほとんど異議申し立ての本はありませんでした。マスコミの動きはもっとひどく、今だにアメリカやそれに追随する小泉首相を賛美しているしまつです。この九月に小泉首相の任期切れとなるので、それに合わせるかのように首相と一定の距離を取ろうとする報道も見られますが、一時の賛美の姿勢を考えると、腰のすわった批判だとはとても思えません。そういう中で、首相を批判する書籍が新書レベルでも出版されるようになっています。頼もしい限りです。しかし、それらの本の中で、今後も長期に読むに耐える本となるとわずかなものでしょう。その理由の一つは、アメリカを批判しようとしても、説得力を持とうとすると、知らない間に、アメリカ的な思考を使って、アメリカを批判することになり、どこかで自己撞着に陥ってしまうからです。現在のアメリカの政策を批判するだけではなく、アメリカの文化を根底から相対化する視点を持つ必要があると思います。ところが、多くの本にはそれが欠けています。 『アメリカに「NO」と言える国』を読ませて頂きました。最近はブッシュ大統領や小泉首相を批判的にとらえる本も少しずつ出版されるようになってきましたが、一時はほとんど異議申し立ての本はありませんでした。マスコミの動きはもっとひどく、今だにアメリカやそれに追随する小泉首相を賛美しているしまつです。この九月に小泉首相の任期切れとなるので、それに合わせるかのように首相と一定の距離を取ろうとする報道も見られますが、一時の賛美の姿勢を考えると、腰のすわった批判だとはとても思えません。そういう中で、首相を批判する書籍が新書レベルでも出版されるようになっています。頼もしい限りです。しかし、それらの本の中で、今後も長期に読むに耐える本となるとわずかなものでしょう。その理由の一つは、アメリカを批判しようとしても、説得力を持とうとすると、知らない間に、アメリカ的な思考を使って、アメリカを批判することになり、どこかで自己撞着に陥ってしまうからです。現在のアメリカの政策を批判するだけではなく、アメリカの文化を根底から相対化する視点を持つ必要があると思います。ところが、多くの本にはそれが欠けています。この本の特徴は、ヨーロッパから見たアメリカという視点で、アメリカとヨーロッパの文化の違いやその意味するものを見据えて、批判がなされている点です。決して読みやすい本とは思いませんが、練られてきた思考が凝縮しているため、読み込むには時間が必要だからでしょう。あるいは、私達が日常使っている思考と違った回路を刺激するからでしょう。思考転換には時間がかかります。ユニバーサリズムとコミュノタリズムという概念も、初めて読むと、すぐには整理して理解することは難しいです。それでも、カトリックという補助線を入れることで、世界史や欧米の歴史・文化の理解が、格段に進むという印象があります。これらは、フランスに住んで、カトリックを思考の枠組みとして生活している著者の力だと思います。 日本人の我々が、この本からすぐに良い智慧を生み出せるとはとても思えません。アジアのここ150年ぐらいの歴史に補助線を引くとしたら、それは何かという答えを仮説でも良いから見つけ出さないと、アメリカに懲りて、フランスに身を任せるということになりかねません。
name:Nao 様 やっと竹下先生のご本を読み終えました。とにかく、興奮してその夜は眠れず、3時ころまでいろいろ考えていました。
私はこの本を読んだあと自分の中に一本のユニバーサリズムという補助線が通った安堵感をもちました。それはまた安心感とともに、個人の犠牲も伴うこともを受け止めなくてはならないということだということもよくわかりました。
やっと竹下先生のご本を読み終えました。とにかく、興奮してその夜は眠れず、3時ころまでいろいろ考えていました。
私はこの本を読んだあと自分の中に一本のユニバーサリズムという補助線が通った安堵感をもちました。それはまた安心感とともに、個人の犠牲も伴うこともを受け止めなくてはならないということだということもよくわかりました。現在の日本が何故こんなに住みにくくなってきたのかを考えるとき、アメリカのコミュニタリズムに影響どころか、汚染されてきたからだ、ということもよくわかりました。現在の小泉政権がネオ・リベラル(市場・経済の自由至上主義)になってしまったこと、その影響が個々人の生活に暗い影を落としていることを知りました。 イラク開戦時、アメリカに同調した日本の姿勢を悲しみつつもアメリカの属国であるような小国日本の選択肢は他にないんだという諦め感が私の中にはありました。大抵の日本人がそう思ったとおもいます。フランスの開戦反対は快なるかなと受け止めながら、そうは言えない辛さをみな持っていたように思います。 その姿勢そのものがコミュノタリズムの影響を受けていたからだということに、今回はじめて思い至りました。ユニバーサリズムの補助線が一本通ると、Bソシアル(フランス型・富を循環分配する福祉型)の社会の姿がうっすら見えてきます。それは個人の内部でまず改革が始まることから見えてくるものなんですね。私の内部に個人を個人として、レスペクトするユニバーサリズムの線があると、随分生きやすいことがわかりました。 老いること、障害をもつこと、それらを体験しながら、世間からの差別の目、行動がよく見えるようになっていましたが、差別という姿勢もユニバーサリズムの補助線が引けると変わってゆくはずだと思います。 少し気になったのはこの本を読んでプロテスタントの方々はどう思われるか、ということです。ピューリタンがいまのアメリカを作ってきたわけですから、どこに指針をもとめればいいのか、カトリックの人々よりは悩みが深いのではないか、と思いました。 この本は名著であるとともに、ある意味での犠牲の子羊的勇気が著者には必要であった事とおもいます。そこに、竹下先生の毅然とした、品性を感じます。かなり難しく、読みきるのに努力が必要ですが、やさしく書くことは至難の業のように思います。 自分の哲学を構築するためにはこの難しい本を完全にマスターして、人に伝えるくらいの努力をしなくてはならないと思いましたし、お互いにこの本を持ち寄って、学習会をする必要があると思いました。 横文字の多いのは少し大変な思いをしました。 いろいろ感じたことはありますが、二つの主義を示して下さったことで、見えなかったものが急に明らかになってくるのは恐ろしいほどです。ありがとうございました。 (2006/3/19) name:J.O. 様 「バロック音楽はなぜ癒すのか」最近、音楽仲間とコレルリ等のバロック・トリオの曲を練習しているが、これらの曲には良く、クーラント、ジグ、サラバンド、アルマンド等々の曲想が出てくる。これらは、バロックバレエに由来するもので、上手く演奏するには、バロックバレエを良く理解した上で演奏するのが良いと云われている。しかし、その方面の知識がなく、これまでその感じが掴めないでいた。
本書は、年末に本屋で見かけたが、バロックバレエの解説の他、著者自身が、ギターによるバロック・トリオや弦楽器をやっているらしく、このことも参考になると思われ、早速購入した。当初、著者は音楽の専門家だろうと思ったが、本を読んだ所、音楽の専門家ではなく、比較文化研究者とのことで、本職の研究以外にバロックトリオを創設し、日本公演を行い、その上、ビオラにも取り組み、かつ、在住されているフランスではピアノを教えている内容が書かれていて、その多才ぶりに驚かされた。
「バロック音楽はなぜ癒すのか」最近、音楽仲間とコレルリ等のバロック・トリオの曲を練習しているが、これらの曲には良く、クーラント、ジグ、サラバンド、アルマンド等々の曲想が出てくる。これらは、バロックバレエに由来するもので、上手く演奏するには、バロックバレエを良く理解した上で演奏するのが良いと云われている。しかし、その方面の知識がなく、これまでその感じが掴めないでいた。
本書は、年末に本屋で見かけたが、バロックバレエの解説の他、著者自身が、ギターによるバロック・トリオや弦楽器をやっているらしく、このことも参考になると思われ、早速購入した。当初、著者は音楽の専門家だろうと思ったが、本を読んだ所、音楽の専門家ではなく、比較文化研究者とのことで、本職の研究以外にバロックトリオを創設し、日本公演を行い、その上、ビオラにも取り組み、かつ、在住されているフランスではピアノを教えている内容が書かれていて、その多才ぶりに驚かされた。バロックバレエに関しては、バロック・ジェスチュエルという技術があるとのことで、これを取り入れた、ご自分のピアノの生徒の指導方法や、弦楽器のレッスンにこの技術を取り入れることで、ボーイングや音程がすんなりとイメージでき演奏が上手く行くようになることなども書かれていて大変、興味深い。また、プロのダンサーに踊って貰いながら、曲を演奏すると、まるでマジックのように曲が手に触れているように感じられたとのことで、このことも面白い。この他、アンサンブルに没頭すると、演奏メンバーの考えていることや、体調などが演奏中に、言葉を交わさなくても分かるようになるばかりでなく、メンバー全員が作曲者がそばにいるように感じることもあるとのことで、このことにも感銘を受けた。 自分のようなアマチュアにはこのようなレベルに至るのは到底難しそうだが、本書の内容に刺激を受け、今後のアンサンブルの練習に役立てたいと思っている。本書は、タイトルに関連する、バロック音楽と心身性のほか、フランスバロックがルソーによって批判を受けて、歴史から一旦消えかかったことなどや、音楽と色彩性、出雲のお国とバロック音楽との関連性など、多岐に亘って触れられておりバロック音楽に関する大変面白い内容であった。 (2006/1/25) じたことはありますが、二つの主義を示して下さったことで、見えなかったものが急に明らかになってくるのは恐ろしいほどです。ありがとうございました。 (2006/3/19) name:GREEN-CURRY 様 竹下様、
「さよならノストラダムス」拝読しました。
最終章の終わりごろからほろっとしてきました。電車の中で読んでいたので焦りました。あぶない、あぶないと自分を制御しつつ読み進んだのですが、カトリックの聖人の祈り
「神よ、私に変えることのできるものを変える勇気をください。
・・・・」(読んでいない方のために省略)
で、ほろほろになってしまい、最後まで読んだときには目がうるうるでした。
こりゃいかんと思い窓の外を見上げると、とんでもなくキレイな夕焼けで、ノストラダムスからのプレゼントかしらと思いました。あまりにきれいな夕焼けの下は、あまりにゴミゴミと密集した大阪の街が広がっていて、その対比に驚き、しかしいやな感じを受けたのでなく、空の大きさや美しさに比べて私たちはあまりに無力だけどそれでもみんな一生懸命生きて生活してるんだなぁと思うとちょっと感動したりしました。ちょっとsensibleになったひと時でした。
(2005/6/6)
竹下様、
「さよならノストラダムス」拝読しました。
最終章の終わりごろからほろっとしてきました。電車の中で読んでいたので焦りました。あぶない、あぶないと自分を制御しつつ読み進んだのですが、カトリックの聖人の祈り
「神よ、私に変えることのできるものを変える勇気をください。
・・・・」(読んでいない方のために省略)
で、ほろほろになってしまい、最後まで読んだときには目がうるうるでした。
こりゃいかんと思い窓の外を見上げると、とんでもなくキレイな夕焼けで、ノストラダムスからのプレゼントかしらと思いました。あまりにきれいな夕焼けの下は、あまりにゴミゴミと密集した大阪の街が広がっていて、その対比に驚き、しかしいやな感じを受けたのでなく、空の大きさや美しさに比べて私たちはあまりに無力だけどそれでもみんな一生懸命生きて生活してるんだなぁと思うとちょっと感動したりしました。ちょっとsensibleになったひと時でした。
(2005/6/6)
|
|
